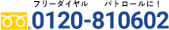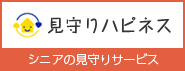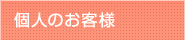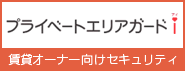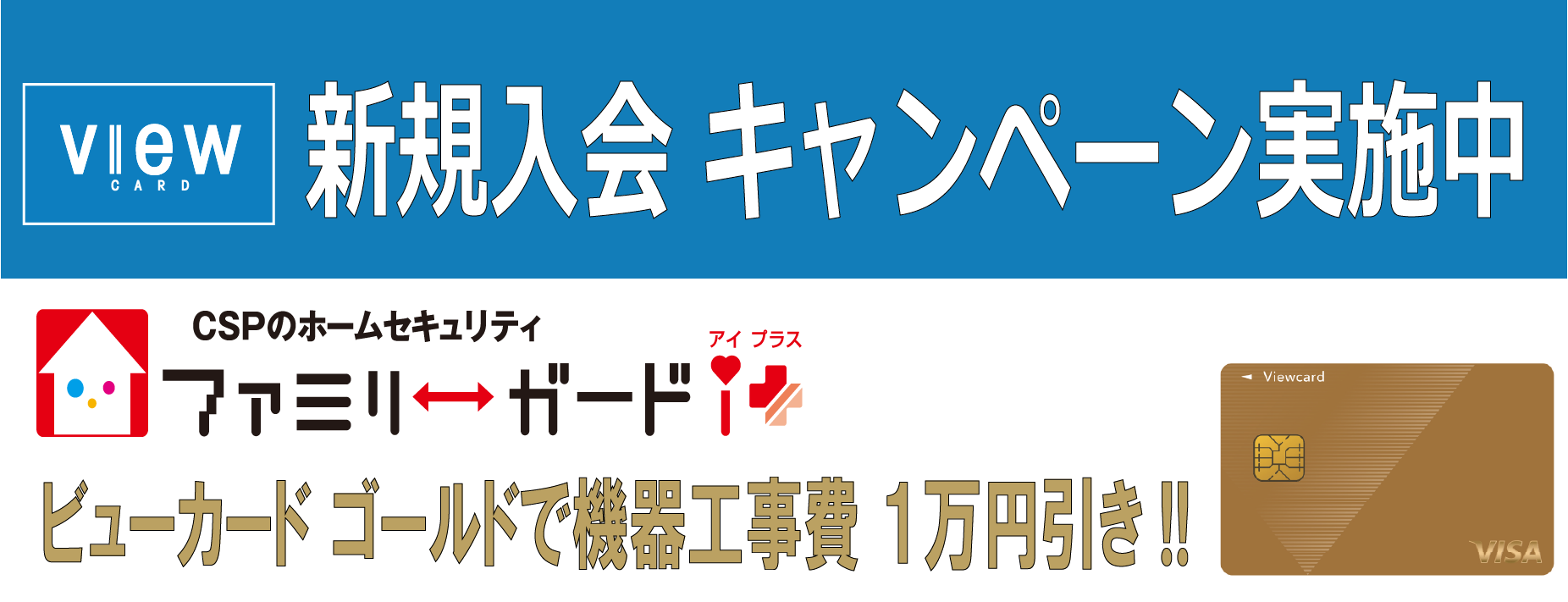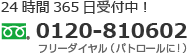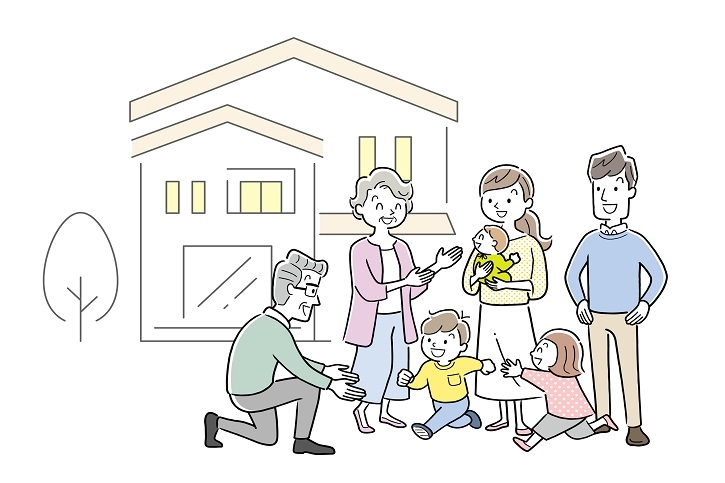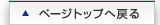CLOSE
- CSP セントラル警備保障 | 警備・防犯・防災・情報セキュリティ >
- 個人のお客様 >
- ホームセキュリティコラム >
- 一人暮らし高齢者の安全を守る防犯対策と見守りサービス
一人暮らし高齢者の安全を守る防犯対策と見守りサービス
更新日:2024年12月 3日
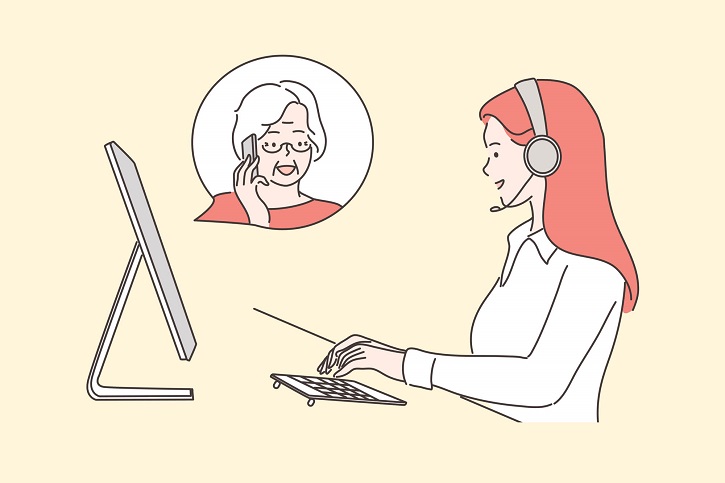
65歳以上の一人暮らしが年々増えています。高齢の両親が今単身生活を送っている、あるいは今後一人暮らしを計画しているということで、暮らしの安全を気にされている方も多いのではないでしょうか。高齢者の一人暮らしにはさまざまなリスクが懸念されることから、住まいのセキュリティ向上やいざというとき助けてもらうためのご近所付き合いが大事になってきます。
こちらでは、一人暮らしの高齢者が犯罪のターゲットになる背景や注意したい犯罪トラブル、自分の身と住まいを守るための防犯対策に加え、問題が起きたとき駆けつけられる見守りサービスについてご説明します。
- 高齢者が犯罪のターゲットになる背景
- 一人暮らし高齢者が注意したい犯罪・トラブル
- 高齢者の一人暮らしで起きやすい事故やトラブル
- 一人暮らし高齢者の防犯対策「住まいセキュリティの向上」
- 一人暮らし高齢者の防犯対策「周囲の協力やサポート」
- 一人暮らし高齢者の日常でできる防犯対策
- 高齢者の安全を守る見守りサービス
- まとめ
高齢者が犯罪のターゲットになる背景
まずは、高齢者が犯罪のターゲットになりやすい理由についてまとめます。もっとも大きな要因は高齢者の単身世帯が増加している点です。一方で、高齢者の身体的能力や習慣、心理なども原因のひとつであると考えられます。
高齢者の単身世帯が増えている
内閣府が発表した「令和5年版高齢社会白書」では、65歳以上の単身世帯の増加傾向が報告されています。昭和55年の段階では、男性が4.3%、女性が11.2%でした。しかし令和2年の調査時には、男性が15.0%、女性が22.1%と大幅にポイントを増やしていることがわかります。
身体能力や判断能力が低下した高齢者は、犯罪者にとって絶好のターゲットです。その人たちが住む世帯が増えていることこそが、高齢者の被害を増やしている原因といえるでしょう。
見つかっても高齢者相手なら逃げやすい
空き巣犯にとって、若年層が住む家と高齢者の住む家とでは、後者のほうが逃亡できる可能性が圧倒的に高くなります。万が一犯行を見られてしまった際、身体能力が低下した高齢者であれば追いかけられることもないと考えるからです。その他にも、視力や聴力が衰えているため、侵入に気付かれにくいともいえるでしょう。
なお、万が一犯行に気がついたとしても、犯人を追いかけるのは非常に危険です。暴行を受けて命を落とすリスクもあるため、絶対に犯人を捕まえるような行動は取らないでください。
不注意やもの忘れで鍵を掛けないことが多い
一部の高齢者の方のなかには、玄関や窓を施錠せずに外出するといった習慣を持つ方も少なくありません。犯人からすると、こうした住まいは侵入がしやすい格好のターゲットです。前述で述べた高齢者世帯が増えていることと合わせて、一人暮らしの高齢者が狙われる原因になっていると考えられます。
特殊詐欺など高齢者を狙った犯罪が増えている
内閣府が発表した特殊詐欺に対する意識調査によると、70歳以上の人の半数以上が「自分は被害に遭わない」と考えていることがわかっています。このように、高齢者は自信の経験から、自分を過信しやすい傾向が読み取れます。その心理を逆手に取った特殊詐欺は多く、結果として高齢者の被害が増えていると読み取れます。
一人暮らし高齢者が注意したい犯罪・トラブル
次に、高齢者の一人暮らしで起こる犯罪・トラブルのリスクについて見ていきましょう。
具体的な被害としては、空き巣や強盗に入られる盗難、訪問販売員との間で起こるトラブル、振り込め詐欺(特殊詐欺)などが思い浮かぶでしょう。高齢者が犯罪被害に巻き込まれやすい実態は、警察庁や内閣府が発表するデータからもわかることです。
もちろん高齢者を一括りに考えることはできません。年齢に関係なく、元気でしっかりした方もいらっしゃいます。ただし、加齢に伴って肉体の衰えと判断力の低下が加速するのは、人間にとって避けられない性質のものですので、そのような事実を踏まえ各種の犯罪トラブルから高齢者を守る対策や取り組みが求められます。
以下では、一人暮らし高齢者が注意したい犯罪・トラブルの具体例をご紹介します。
空き巣窃盗・強盗被害
単身世帯の高齢者は、侵入窃盗や侵入強盗の被害リスクが高まります。確実に物を盗んで逃げきりたい犯人からすれば、家族で暮らす家より一人暮らしの高齢者宅のほうが犯行を遂げやすいと考えるでしょう。相手が高齢者一人なら何とか切り抜けられると考え、強引に押し入る可能性もあります。
泥棒は、不在時に忍び込む空き巣ばかりとは限りません。在宅時を狙って盗みを働く「居空き」も存在します。犯行現場に出くわしてしまうと、犯人から思わぬ危害を加えられる恐れもあります。こうなると窃盗ではなく強盗傷害事件へ発展し、命の危険にさらされる可能性もあるということです。
訪問販売トラブル
高齢者の悪質な訪問販売トラブルに関する被害相談が増えているといわれます。
悪質商法の手口は多様化・巧妙化が進んでおり、扱う商品もさまざまです。住宅リフォームや浄水器、布団、着物、健康食品などを勧めてきて、言葉巧みに購入契約へと誘導します。床下や水道、屋根を無料点検すると言いながら、点検後に修繕や商品の契約を取り付ける訪問販売ビジネスもあります。高齢者が無警戒なのをいいことに、一度契約を取り付けた後何度も訪れて次から次へと商品を買わせる手口も、彼らの得意とするところです。
高齢者は、健康やお金、孤独に不安を抱えやすいものです。そのため、親切にされると簡単に人を信用してしまう状況にあります。悪徳業者はそこに目をつけて言葉巧みに接近し、高齢者の大切な貯金や財産などを奪おうとします。強引な勧誘や身分の詐称、虚偽説明を行ってだます手口もみられます。トラブルに遭わないためには、高齢者が狙われやすい実態と、悪徳業者・悪質商法の手口に関する情報を知ることが大切です。
特殊詐欺
特殊詐欺といえば、オレオレ詐欺や架空請求詐欺、融資保証詐欺、還付金詐欺などの「振り込め詐欺」による被害が有名です。内閣府の調査によると、今でも高齢者を中心とする特殊詐欺は1日あたり約1億円もの被害を生んでいるとのことです。
令和4年(2022年)における特殊詐欺の高齢者被害率をみると、65歳以上の割合は86.6%。高齢者が被害当事者となりやすいのは、オレオレ詐欺(98.2%)、預貯金詐欺(98.7%)、キャッシュカード詐欺盗(98.9%)ということがわかっています。
参考までに、振り込め詐欺の特徴について触れておきます。
- オレオレ詐欺:親族を装って電話を掛け、指定の預金口座にお金を振り込ませる手口
- 還付金詐欺:自治体の職員を名乗る者が電話を掛けてきて、医療費の還付金が戻るなどとだましてATMを操作させ、指定口座にお金を振り込ませる手口
- 架空請求詐欺:架空の請求書を送りつけて指定口座に現金を振り込ませる手口
- 融資保証金詐欺:融資すると偽って保証金の支払いを要求し、指定口座に現金を振り込ませる手口
自治体や税務署、年金事務所などの職員が電話を掛けてATMを操作させるといった真似は考えられませんので、だまされないよう注意しなければなりません。
出典:警察庁・SOS47 特殊詐欺対策ページ(特殊詐欺の手口と対策)
高齢者の一人暮らしで起きやすい事故やトラブル
高齢者が直面するリスクには、家庭内事故、孤独死、認知症、健康トラブルなどが挙げられます。これらのリスクを軽減するために、家族や地域社会、自治体が連携して見守り体制を整えることが重要です。
家庭内事故
高齢者の転倒は、外傷だけでなく、長期入院による筋力低下や認知症リスクを高めます。転倒の恐怖心から自宅に閉じこもりがちになり、最終的には寝たきりになる方も少なくありません。
東京消防庁の調査によれば、令和4年には61,507人の高齢者が転倒事故で救急搬送され、その多くが自宅内で発生しています。転倒の主な場所は居室や玄関、廊下で、下肢筋力の低下や視力の問題が原因であることが多い傾向にあります。
転倒防止には、環境の整備や筋力アップが重要です。例えば、手すりの設置や段差の解消、滑りにくい靴の使用、ストレッチの習慣化が有効とされています。
孤独死
高齢者の一人暮らしは孤独死のリスクを高める原因のひとつとして考えられます。
特に近年は高齢者の一人暮らしが増加しており、それに伴って孤独死とみられる事例も増えています。実際、東京23区では65歳以上の一人暮らしの高齢者が自宅で亡くなるケースが年間で3000件を超えており、この数は年々増加しています。
家族が近くにいない場合、地域の協力を得て見守りを行うことが理想ですが、現実には難しいことも多いでしょう。孤独死を防ぐためには、家族や地域、自治体が連携し、見守り体制を整えることが重要です。例えば、地域での見守り活動や緊急連絡システムの導入など、さまざまな対策を検討する必要があります。
認知症
認知症による判断能力の低下は、日常生活への意欲喪失の原因となります。物事の計画や意思決定が難しくなり、活動や趣味への関心が薄れ、生活の質が低下するためです。外出を避けたり人との交流を控えたりして、孤立感が強まる方も少なくありません。
また、認知症が進行すると、約束や予定を忘れてしまい家族や友人との関係に影響が出たり、金銭管理ができず家計が乱れたりすることもあります。安全を確保する判断が難しくなり、交通事故や火災などの危険も増える傾向にあります。
健康問題
冬の感染症リスクや寒暖差による健康トラブルは、高齢者にとって大きな問題になり得ます。持病がある高齢者は軽い感染症でも重症化しやすく、ヒートショックによる健康被害も心配されます。
冬は気温が低く身体が冷えやすいため免疫力が低下しやすく、暖房器具の使用で空気が乾燥すると、インフルエンザや風邪のリスクが増します。さらに高齢者はインフルエンザから肺炎を引き起こしやすく、重症化リスクも高いためより注意しなくてはなりません。
ヒートショックを防ぐためには、浴室や脱衣所の暖房を心がけ、屋内の温度差を減らす工夫が必要です。さらに、空気の乾燥による皮膚トラブルや低温やけど、屋外での転倒事故にも注意が必要です。家族が高齢者を見守り、早期に問題を発見し対処することが重要です。
一人暮らし高齢者の防犯対策「住まいセキュリティの向上」
犯罪被害から一人暮らし高齢者を守るために必要なのが防犯対策です。ここでは、防犯カメラやワンドアツーロック、窓ガラス防犯などセキュリティ向上につながる対策をご紹介していきます。高齢の両親の暮らしに不安を覚える方は、ご本人に勧めてみてください。
防犯カメラ
防犯カメラのある家はそれだけでセキュリティ意識の高さの裏付けとなり、空き巣や強盗犯にプレッシャーを与えることができます。訪問販売の悪徳業者も、防犯カメラの記録に残ることから大胆な真似はできないと訪問を避けてもおかしくありません。
防犯カメラを設置する場合、効果を考えたうえで場所を検討しましょう。玄関先や死角を生みやすいトイレ・浴室の窓付近、ベランダなどに設置すると抑止力が高まります。防犯カメラがあることをアピールするため、「防犯カメラ稼働中」のステッカーで周知することも大切です。予算の関係で複数の設置は厳しいかもしれませんが、その場合はダミーとの併用を検討してみてください。ダミーカメラで補う場合は、手の届かない場所に設置するなどダミーと悟られないような工夫も忘れないようにしましょう。
ドア鍵の対策強化
玄関ドアや裏口などの出入口の鍵を違法な手口で解錠されないような対策も有効です。この対策には2点のポイントがあります。
一つ目は、「ワンドアツーロック」です。補助錠をつける対策で、ドアの鍵が二重になって違法解錠が難しくなります。解錠に時間がかかるとわかれば空き巣も侵入をあきらめるでしょう。侵入に10分以上時間がかかる場合ほとんどの空き巣はあきらめるとのデータもあります。
二つ目は、鍵そのものを交換したりガードプレートを取り付けたりするなどして、ピッキングやドア破りしにくいドアにすることです。昔ながらのディスクシリンダー錠を採用している家はピッキングで簡単に解錠されてしまいます。古い鍵の交換がお済みでない場合はピッキング対応のディンプルキーへの交換がおすすめです。バールなどの工具で強引にドア破りされない対策としては、ドア枠とドアの隙間を塞ぐ「ガードプレート」の使用が有効です。
なお、このような対策を施しても鍵を掛けない「無締まり」では意味がありません。実際、泥棒に入られやすい一番のタイミングは、鍵を掛けないで出かけたときです。ほんの少し家を離れるときでも鍵を掛けることを忘れないよう注意してください。
窓の対策
窓は、空き巣や泥棒がもっとも好んで使う侵入ルートです。窓ガラスを強化して侵入を困難にさせる対策には、「防犯ガラスへの交換」「防犯フィルムの貼付」「補助錠の取り付け」などがあります。また、雨戸・シャッターの設置、格子窓や二重窓なども有効な対策になるでしょう。いずれの方法も、侵入に時間がかかってあきらめさせる効果を狙うということです。
予算にも限りがあるでしょうから、すべての窓に対策を施すのは難しいかもしれません。縁側の掃き出し窓や寝室の窓など、狙われやすいポイントに重点を置いての活用が望まれます。かといって、トイレ用のような小さい窓から侵入してこないとも限りません。その場合は防犯カメラや侵入感知センサー、威嚇ブザーなど他のアイテムの使用で弱点を補うとよいでしょう。
防犯アイテムの活用
上記でご紹介した対策のほか、さまざまな防犯アイテムの活用で住まい環境のセキュリティを強化できます。
- センサーライト:近づく物に反応して光を当てる防犯用の照明器具
- 威嚇ブザー:大音量を流して犯人を怯ませる効果あり
- 防犯砂利:足音が響きやすくなる砂利。空き巣対策に有効
一人暮らし高齢者の防犯対策「周囲の協力やサポート」
一人暮らしの高齢者を侵入窃盗や強盗などの犯罪から守るには、住まいのセキュリティ向上だけでは足りません。周囲の協力やサポートも必要です。具体的にどのようなサポートがあるか以下でご説明します。
近隣住民の助けを借りる
空き巣は、ターゲットにする家を事前に下見する際、その地域に住民同士の連帯意識があるかどうかをみるといわれます。地域の連帯感が強い街で不審な動きをすると声をかけられる恐れが高くなるため、住民同士の立ち話や声かけのないような環境を狙うというわけです。
この点を踏まえると、一人暮らしの高齢者の空き巣被害リスクを減らすには、近隣住民との関係性が重要になってきます。
住民同士の良好なコミュニティを構築し、いざというときサポートを受けられるようにするには、日頃からあいさつやコミュニケーションを大事にするのが理想です。高齢の両親が一人暮らしをはじめる際に家族の方が近所を訪ね、できれば協力してもらえるようお願いする方法もあっていいでしょう。最初に地ならしをしておくことでその後の関係を良好に保てます。
行政・民間の見守りサービスの活用
一人暮らしの高齢者が増えた現実を受け、自治体では高齢者の孤立を防ぐための見守りサービスを実施しています。体調の急変や転倒、火の不始末やガス漏れ、不審者の侵入など、異変が起きたとき迅速に対応するためのサービスです。
自治体によって細かいサービス内容や条件は異なりますが、共通するのは地域での見守りのサポートが受けられる点です。見守り要員と呼ばれる人たちが高齢者宅を訪問・巡回し、異常や異変がないか確認します。そこにはライフライン事業者や民間の会社がバックアップする面もあり、官民一体の見守りサービスです。地域住民も監視の目として加わってくれるので、犯罪抑止の効果は大きなものがあります。
介護サービスの活用
在宅介護サービスは、要介護認定を受けた方が、介護保険の範囲内で身の回りの世話や生活援助に関するサービスを受けるというものです。介護スタッフの定期的な訪問による孤立防止に加え、誰かの訪問や出入りのある家は監視の目が働くため、侵入窃盗や訪問販売トラブルなどの被害リスクの軽減につながります。
一人暮らし高齢者の日常でできる防犯対策
上記のとおり、周囲の協力とサポートは防犯性能を高めるうえで非常に重要です。一方で、一人暮らしの高齢者が自身で対策を講じることも大切です。以下では、日常でできる手軽な防犯対策をご紹介します。
必ず施錠する
警察の調査によると、侵入窃盗の多くは「無締まり」と呼ばれる手口で行われています。これは、鍵を掛けていない玄関や窓からの侵入手口のこと。例えばゴミ出しなどの短時間の外出時が、犯罪者にとって絶好のチャンスとなります。
対策としては、短時間の外出であっても、しっかりと鍵を掛ける習慣をつけることです。防犯対策の基本として、常にドアや窓の鍵を確認し、確実に施錠することを心がけましょう。このちょっとした心がけが、大切な財産や安全を守ることにつながります。
留守中でも灯りをつける
空き巣は家人の留守を狙って不法侵入を行います。逆を返せば、在宅であることがわかっていると、侵入リスクを減らせるということです。
そのための対策方法が、留守中でも灯りをつけておく、ということです。夜間であれば在宅を装えますし、窓の外が明るくなるため不審者の行動抑止にもつながります。
高齢者が一人で住んでいることを知られないようにする
高齢者だけの世帯は空き巣に狙われやすい傾向にあります。そのため、家族構成がわからないように工夫することも防犯につながります。
例えば、表札は出さないか、出しても名字だけにすることで家族構成を隠せます。また、複数の部屋の灯りをつけておくことで、家族がいるように見せかけることもできます。このように、家の外から見たときに家族が住んでいるように装うことで、不審者に狙われるリスクを減らせます。
訪問相手を確認してからドアを開ける
空き巣のなかには、宅配業者や水道・ガスの検査員などを偽って侵入を試みる者も存在します。そのため、初めての訪問者には特に注意が必要です。
来客時には、まずモニター付きのインターフォンやドアチェーンを使い、顔や身分証を確認してから対応することを心がけましょう。宅配便や届け物の場合、「どこの誰から誰宛ての荷物か」を確認し、ドアチェーンを掛けたままで受け取ることが重要です。不審に感じた場合は、荷物を受け取らずに持ち帰ってもらうか、置き配にしてもらうようにしましょう。
高齢者の安全を守る見守りサービス
前述した見守りサービスは、自治体が実施するだけでなく、民間企業が独自に提供するサービスもあります。見守りの主な内容は、人感センサーを使って高齢者宅の異変・異常を素早く検知し、通報や緊急対応のシステムを確立するというもの。CSPにはシニアの暮らしを24時間365日見守る『見守りハピネス』があります。
人感センサーを屋内に配置して、高齢者の生活反応を見守るシステムです。緊急通報ボタンを押せばCSPに通報され、パトロール員が駆けつけてくれます。もし家の周囲で不審な動きがあったり、不審人物の訪問や侵入があったりした場合にも緊急通報ボタンを押して助けを求めることができるのです。
犯罪抑止効果はもちろん、体調の急変や持病の悪化、転倒、あるいは火災・ガス漏れなどの家庭内事故にも迅速な対応が期待できます。家族と離れ一人で暮らす高齢者の方におすすめのサービスです。
まとめ
高齢者の一人住まいは、盗み目的の侵入犯からすれば狙いやすくなるため、注意しなければなりません。オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺、弱者に目をつけてだます悪徳業者の訪問にも備える必要があります。どのような手口があり、どのような状況だと被害に遭いやすいか把握したうえで有効な対策を考えましょう。空き巣対策としてとり入れたいのは、住まいのセキュリティを向上させる防犯アイテムの活用です。行政や警備会社の見守りサービスには周りの人たちがサポートしてくれる心強さがあります。
CSPの『見守りハピネス』は、24時間365日、日々の生活反応を確認して、困った際には駆けつけてくれるサービスです。目の届かない場所に暮らす両親の安全・安心のためにお使いください。
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の詳細ページはこちら↓
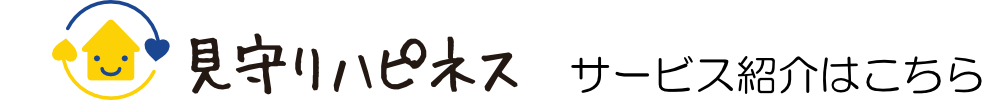
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ」
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の資料請求やお見積り依頼はこちら↓
おすすめ記事