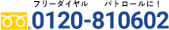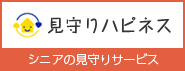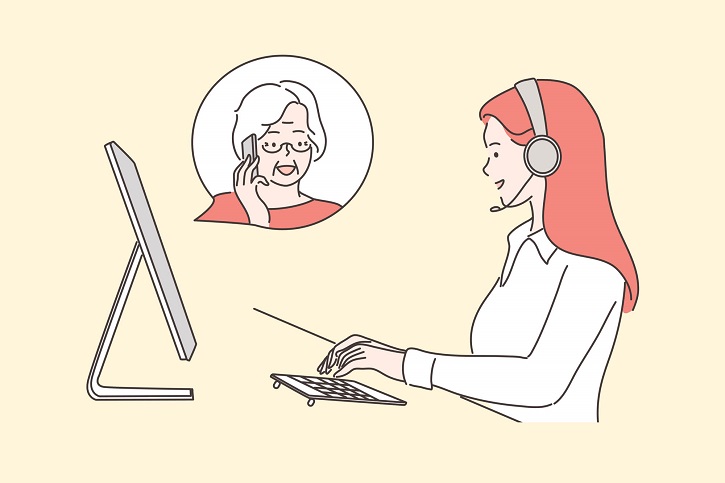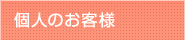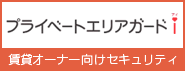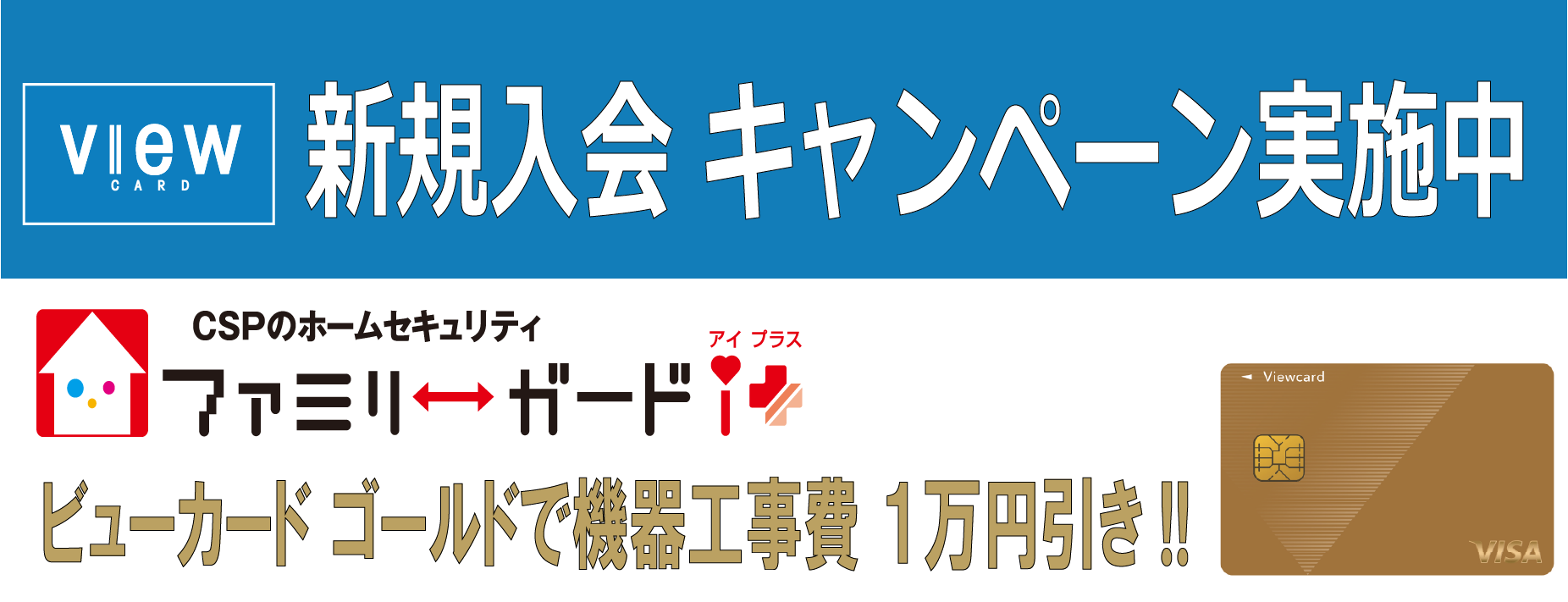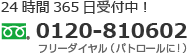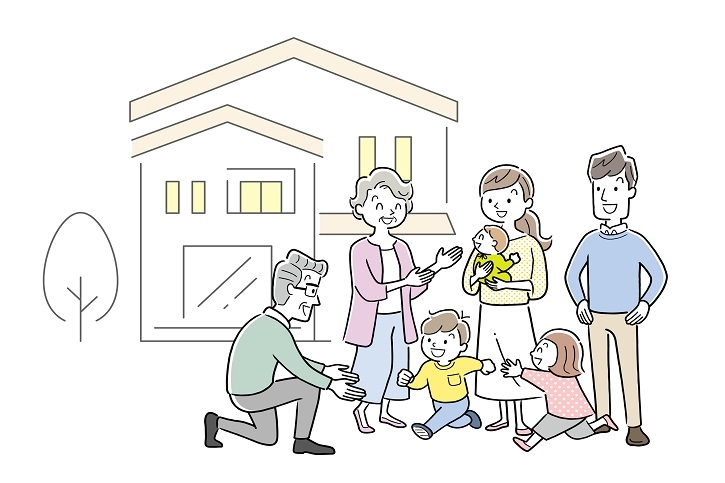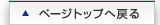CLOSE
- CSP セントラル警備保障 | 警備・防犯・防災・情報セキュリティ >
- 個人のお客様 >
- ホームセキュリティコラム >
- 介護拒否はなぜ起きる?よくある7つの原因と上手な対応方法を解説!
介護拒否はなぜ起きる?よくある7つの原因と上手な対応方法を解説!
更新日:2025年1月18日

「介護拒否されてつらい」
「介護拒否されたときの対応方法が分からない」
「介護拒否される理由を知りたい」
とお悩みではありませんか?
介護拒否が起きる原因はさまざまですが、上手な対応方法を知っておけば、思うように介護を進められない悩みの解消につなげられます。
ここでは、介護拒否のよくあるケースと起きる理由から、上手な対応方法や介護拒否に関するよくある質問まで分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
- 介護拒否とは?
- よくある介護拒否のケース
- 介護拒否が起きる7つの原因
- 介護拒否への上手な対応方法
- 介護拒否されてつらいときは?
- 介護拒否対策には「高齢者の見守りサービス」も有効
- CSPの見守りサービス「見守りハピネス」がおすすめ
- 介護拒否に関するよくある質問
- まとめ
介護拒否とは?
介護拒否とはその名のとおり、介護が必要な高齢者が、介護サービスや支援を受けることを拒否することを指します。
代表的な例として、食事や入浴、着替え、トイレなどの日常生活に欠かせない動作の拒否が挙げられます。また、服薬の拒否など、病気の治療に関わることを拒否するケースも少なくありません。
介護拒否が引き起こされる要因は、本人の意思や感情、過去の経験、介護者との関係など多岐にわたります。介護拒否が発生すると介護がスムーズに進まなくなるため、介護者や家族にとって大きな負担となり、適切なケアを提供することが難しくなってしまいます。
介護拒否に対処するためには、原因の見極めが欠かせません。次の項目では、よくある介護拒否のケースについて詳しくご説明します。
よくある介護拒否のケース
介護拒否はさまざまなシーンで起こります。よくある介護拒否のケースと対応方法をご紹介しますので、早速見ていきましょう。
食事の拒否
食事の拒否は、介護が必要な方が食事を拒むケースです。
食事の拒否は、食欲不振や食事の内容に対する不満、食事の時間や環境が合わないことなどが原因となります。認知機能の低下により、食べ物を認識できなくなることも一因です。
食事の拒否への対策としては、食事の内容や時間を工夫したり、食事の環境を整えたりしましょう。食事を楽しい時間にするために、家族や介護者が一緒に食事をすることも効果的です。
また、体調などが原因で、食事を拒否することもよくあります。体調や入れ歯の具合、口内炎の有無などチェックしましょう。
入浴の拒否
介護拒否で多いのが、介護が必要な方が入浴を拒むケースです。入浴の拒否は、入浴に対する恐怖心や羞恥心、体調不良、入浴の手順が分からないことなどが原因となります。
入浴の拒否への対策としては、入浴の手順を丁寧に説明し、安心感を与えましょう。また、本人の習慣に合わせて入浴の時間や頻度を調整し、無理のない範囲で入浴を促すことも効果的です。
入浴の際には、音楽やアロマなどで入浴を楽しむ環境や入浴補助具をつけ介護を受ける人の負担を減らすなどの工夫が求められます。
着替えの拒否
着替えの拒否は、介護が必要な方が着替えを拒むケースです。認知機能が低下してくると、着替えの意味が分からなくなることがあります。
着替えの意味が分からない状態で服を脱がされるため、強い不安を感じてしまうのです。対策としては、洗濯や外出など、着替える目的を丁寧に説明しましょう。
また、肩が上げにくくなっていたり、関節の可動域が狭くなっていたりと、身体的な原因で着替えを拒否する場合もあります。うまく着替えられない場合は、着替えやすいように段取りを整え、スムーズに着替えられるような工夫が必要です。
トイレ拒否
トイレ拒否は、介護が必要な方がトイレを使用することを拒むケースです。認知機能が低下すると、尿意や便意を感じにくくなるだけではなく、トイレのやり方が分からなくなることもあります。
トイレの介助は本人のプライバシーや尊厳に大きく関わるため、羞恥心から拒否されることも少なくありません。本人の気持ちに配慮しつつ、声かけや支援を行いましょう。
トイレの支援では多くの工程を適切にこなす必要があるため、どの段階で介助が必要なのかを見極めなければなりません。また、トイレの時間や頻度を調整し、無理のない範囲でトイレを促すことも効果が期待できます。
服薬の拒否
服薬の拒否は、介護が必要な方が薬を飲むことを拒むケースです。「薬を飲む必要性が理解できない」という心情や、薬に対して悪いイメージを持っていることが原因となります。
服薬の拒否への対策としては、服薬の効果や必要性を丁寧に説明し、安心感を与えましょう。また、薬を飲みやすい形に変更することも効果的です。
ただし、服薬を拒否するからといって、食べ物や飲み物に混ぜる行為はNGです。薬の効果が得られなくなったり、食事の味が変わって食事を拒否したりする可能性があります。
服薬を拒否して時間どおりに薬を飲めない場合は、必ず医師に相談しましょう。
外出の拒否
そもそも、年齢を重ねていくと、外出すること自体を面倒に感じる傾向が見られるようになります。加えて、認知機能や身体機能の低下、外出先への不安なども、外出を拒否する原因となります。
外出の拒否への対策としては、外出する目的や行き先などを丁寧に説明しましょう。また、デイサービスなどの介護施設に通っている場合は、施設と相性が合わなかったり、他の利用者とうまくコミュニケーションが取れなかったりすることも理由として考えられるため、しっかりと話を聞くことが大切です。
介護拒否が起きる7つの原因
介護拒否が起きる原因はさまざまですが、主な7つの原因を詳しくご説明します。
認知機能の低下
介護拒否が起きる原因として挙げられるのが、認知機能の低下です。
認知機能が低下すると、周囲の状況や自分の置かれている状況を正しく理解できなくなることがあります。認知症などの病気により、記憶力や判断力が低下し、介護の必要性や意味を理解できなくなり、拒否反応を示してしまうのです。
例えば、食べ物を「食べ物」と認識できないために食事を拒否することもあれば、必要性を感じないために入浴やトイレを拒否することもあります。
認知機能の低下が原因の場合は、本人に必要性などを丁寧に説明しましょう。
強い羞恥心
強い羞恥心も介護拒否の原因です。特に、排泄や入浴など、プライバシーに関わる介護が必要な場合、羞恥心から拒否することがあります。
例えば、トイレの介助を受けることに抵抗を感じてトイレを拒否したり、裸を見られるのが恥ずかしくて入浴を拒否したりしてしまうのです。
羞恥心が原因の場合、本人の気持ちを配慮しない一方的な介助では拒否感が強まるだけです。プライバシーの配慮に欠けた言動をしないよう注意しましょう。
高い自立心やプライド
高い自立心やプライドも介護拒否の原因となります。これまでの人生を自分の力で生きてきた方にとっては、「介護を受ける=自立心を損なわれる」と感じられ、プライドが傷つけられると捉えてしまう場合があるからです。
例えば、着替えの介助を受けるとプライドが傷つけられるように感じることで、着替えを拒否する場合があります。また、排便や排尿の失敗を知られたくないために入浴やトイレを拒否する場合も多いです。
高い自立心やプライドが原因の場合は、本人の自立心を尊重し、できることは本人に任せ、できない分だけサポートするように心がけましょう。
介護生活への不満
介護拒否の原因として、介護生活への不満も挙げられます。介護を受ける生活は自由が制限されるため、ストレスがたまりやすいものです。
その不満が、介護への拒否につながることもあります。例えば、家の味と違う食事に対する不満から食事を拒否したり、昼間にお風呂に入る習慣がなかったことから入浴を拒否したりしてしまうのです。
介護生活への不満が原因の場合は、本人の意見や思いを聞き、できるだけ改善するよう努めましょう。
不慣れな施設での生活
不慣れな施設での生活も介護拒否の原因となります。慣れ親しんだ自宅から介護施設に入所したり、在宅介護で介護者が頻繁に出入りしたりすると、環境の変化に戸惑って介護を拒否してしまうのです。
不慣れな施設での生活が原因の場合は、本人が新しい環境に慣れるまで、時間をかけてサポートする必要があります。
服薬の影響
介護拒否の原因として、服薬の影響も挙げられます。薬の副作用や味が原因で、服薬を拒否するケースも少なくありません。苦手な味や飲み込みにくい形状の薬には、拒否感を覚えさせてしまうでしょう。
服薬の影響が原因の場合は、医師と相談しましょう。味や形状が原因であればそれらを変更できないか、副作用が原因であれば量や種類を変更することで副作用を軽減できないか、本人の意思を尊重しつつ相談しましょう。
体調や気分が悪い
体調や気分が悪いことも、介護拒否の原因の一つです。体調が悪かったり、気分が優れなかったりすると、介護への協力を拒否することがあります。
例えば、体調が悪くて食事をとる気になれないと食事の拒否が起こります。体調や気分が原因の場合は、本人の体調や気分を考慮し、無理のない範囲で介護を行いましょう。
介護拒否への上手な対応方法
介護拒否には何らかの理由があるため、決して無理強いしてはいけません。介護拒否への上手な対応方法をご説明します。
体調や気分を確認する
介護拒否が起きた場合、まずは本人の体調や気分を確認しましょう。体調不良や気分の落ち込みが原因で、介護を拒否することが多いからです。
食事を拒否する場合は、食欲不振や胃の不調が原因かもしれません。無理に食事をとらせるのではなく、体調が回復するまで待つ必要があります。
また、気分が落ち込んでいる場合は、リラックスできる環境を整えたり、気分転換を図ったりすることが効果的です。
介護の必要性を伝える
本人が介護の必要性を理解していない場合に起きる介護拒否では、介護の必要性を丁寧に伝えることが重要です。
入浴を拒否する場合は、入浴の重要性や清潔を保つことの利点を説明します。無理に説得するのではなく、本人の理解を得ることを目指しましょう。
本人の気持ちや意向を尊重する
介護拒否が起きた場合、本人の気持ちや意向を尊重することが大切です。強制的に介護を行うと、さらに拒否感が強まることがあります。
トイレの介助を拒否する場合は、プライバシーを尊重し、できるだけ自力で行う範囲を広げるようにします。本人の意向を聞き入れ、可能な限り望みに沿った介護を提供するように心がけましょう。
タイミングを変えて根気よく声かけする
タイミングを変えて根気よく声かけをすることも、介護拒否に効果的です。
食事を拒否する場合は、時間を置いて再度声かけを行うことで、食欲が戻ることがあります。また、入浴を拒否する場合も、時間を変えて再度試みることで、入浴の意欲が湧くことがあります。
根気よく声かけを続けることで、本人の気持ちが変わることがあるため、一度で諦めないことが大切です。
介助の前に何をするか伝える
介助の前に、何をするかを伝えることは非常に重要です。何をされるのか分からないと、不安や恐怖を感じるのは当然です。
例えば着替えの介助を行う前に、どのような手順で行うかを言葉とジェスチャーを交えて説明することで、内容が伝わりやすくなります。言葉だけではなく、身ぶり・手ぶりを取り入れることで理解が深まり、介護拒否の減少につなげられます。
できることを一緒に見つける
本人が自分でできることを一緒に見つけることも、介護拒否を減少させる方法の一つです。トイレの介助を拒否する場合は、本人が自分でできる範囲を広げることで、プライドを保ちながら介助を受け入れてもらえます。
また、本人が自分でできることを見つけられると自信にもつながるため、介護に対する抵抗感が減るでしょう。
介護サービスの利用を検討する
介護拒否が続く場合、介護サービスの利用を検討することをおすすめします。介護のプロは、介護拒否に対する適切な対応方法を知っており、本人の気持ちに寄り添った介護の提供が可能です。
訪問介護サービスを利用すれば、自宅で安心して介護を受けられますし、デイサービスを利用すれば、ほかの利用者との交流を通じて気分転換を図れるでしょう。
行政機関に相談する
介護についての悩みや問題は、行政機関に相談することで解消するかもしれません。自治体の介護相談窓口や地域包括支援センターなどに相談すれば、専門の相談員が対応してくれます。
介護保険の利用方法の説明や介護サービスの紹介を受けられるだけではなく、介護者の負担を軽減するための支援策など、介護について何でも相談できますので、ぜひ活用しましょう。
施設への入居を検討する
介護拒否が長期にわたって続いており、自宅での介護が難しいと思うようになった場合、施設への入居を検討しましょう。介護施設では、専門のスタッフが24時間体制でさまざまな介護サービスを提供しており、本人の安全と健康を守れます。
介護施設と一口にいっても、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなど、さまざまな種類があるので、本人の状態に応じて適切な施設を選びましょう。また、施設への入居を検討する際には本人の意向を尊重し、納得のいく形で進めることが大切です。
介護拒否されてつらいときは?
介護は毎日休みなく続くため、つらいと感じることもあるでしょう。介護拒否されてつらいときの対処方法をご紹介します。
周りの人に相談する
介護拒否に直面してつらいときは、一人で抱え込まずに周りの人に相談しましょう。家族や友人、介護の専門家に話を聞いてもらうことで、気持ちが軽くなることがあります。
また、同じような経験をしている人たちと情報を共有することで、新しい視点や解決策を見つけられるかもしれません。介護についての悩みは、自治体の高齢者福祉課や地域包括支援センターでも対応してもらえるため、ぜひ利用しましょう。
自分を責めない
介護拒否に直面すると、「自分の介護方法が間違っているのではないか」と自分を責めてしまうことがあります。しかし、介護拒否は介護を受ける側の心理的・身体的な状態によるもので、介護者の責任ではありません。
自分を責めずに冷静に状況を見つめ直し、適切な対応を考えることが大切です。
無理に対応しようとしない
介護拒否が起きたときに無理に対応しようとすると、かえって状況が悪化することがあります。本人の気持ちや状態を尊重し、無理に介護を進めないことが大切です。
介護スキルを身に付ける
介護拒否に対処するためには、介護スキルを身に付けることが有効です。介護の基本的な知識や技術を学ぶことで、介護を受ける側の気持ちに寄り添った対応ができるようになります。
レスパイトケアを行う
レスパイトケアとは、介護者が一時的に介護から離れて休息を取るためのサービスです。介護拒否に直面して疲れたときは、レスパイトケアを利用して、自分自身をリフレッシュさせましょう。
介護者の負担を軽減する主な介護サービスには、デイサービスやショートステイ、訪問介護などがあります。レスパイトケアは介護保険の対象となることが多く、介護保険を利用してサービスを受けられます。
具体的な利用方法や費用については、地域包括支援センターやケアマネージャーに相談しましょう。
介護拒否対策には「高齢者の見守りサービス」も有効
介護拒否対策には、見守りサービスが有効です。
見守りサービスには、センサーやカメラで生活を確認するものや、お弁当の配達を通じて健康状態を確認するものなど、さまざまな種類があります。一般企業だけではなく自治体も見守り活動に取り組んでおり、ライフライン事業者や郵便事業者と提携して各戸訪問や巡回を行うことで、高齢者宅で異常が確認された際に通報できる体制が整っています。
介護の悩みや問題を抱えている場合は、このようなサービスを利用することを検討しましょう。
CSPの見守りサービス「見守りハピネス」がおすすめ
見守りサービスの導入をお考えなら、CSPの「見守りハピネス」をおすすめします。見守りハピネスは、シニアの生活を24時間365日見守るサービスです。
急なケガや体調不良が起こった際に緊急ボタンを押すと、パトロール員が駆けつけます。また、センサーが無反応の場合も、自動的に通知されるため安心です。
見守りハピネスでは、無料の健康相談サービスや、日常のトラブル対応などのオプションサービスも提供されているため、利用者の生活を幅広くサポートできます。
介護拒否に関するよくある質問
介護拒否はなぜ起きるの?
介護拒否は、自尊心や羞恥心、介護者とのコミュニケーション不足などが原因で起こることがあります。また、認知症や精神的な問題が影響することもあります。
介護拒否のよくあるケースは?
- 食事の拒否
- 入浴の拒否
- 着替えの拒否
- トイレ拒否
- 服薬の拒否
- 外出の拒否
などが挙げられます。
介護拒否された場合の対応方法は?
介護を無理強いするのではなく、本人の意思を尊重しましょう。介護を拒否する理由を聞くなど、コミュニケーションを取って信頼関係を築くことが大切です。
また、介護の専門家や医師に相談することで、適切な対応策を見つけられます。
まとめ
介護拒否は毎日の生活のさまざまなシーンで起こり、原因は人それぞれ異なります。認知機能の低下や羞恥心、介護生活への不満、服薬の影響が原因となり、介護拒否する人もいます。
介護拒否は介護する人にとって大きなストレスになりますが、決して怒ったり無理に従わせたりしてはいけません。本人の気持ちや意思を尊重したり、タイミングを変えて根気よく声をかけたりと、冷静な対処を心がけましょう。まずは原因を突き止め、それに合う対策を考えることから始めてください。
自分たちで介護拒否に対処するのが難しい場合は、介護の専門家への相談が適切です。全国にある地域包括支援センターへの相談や、有料老人ホームや介護施設などの利用で解決できる可能性があります。本人が施設への入居を拒む場合は、ご自宅で生活しながらサポートが受けられる見守りサービスの利用を検討してみてください。
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の詳細ページはこちら↓
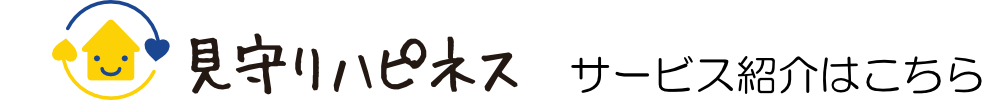
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ」
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の資料請求やお見積り依頼はこちら↓
おすすめ記事