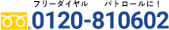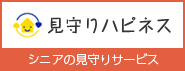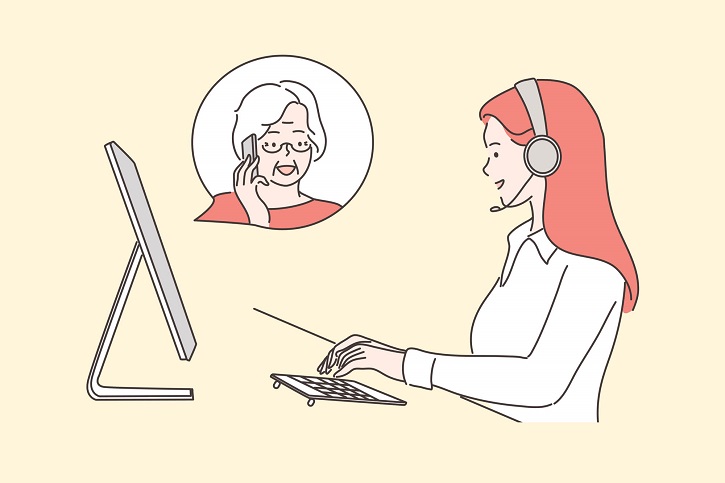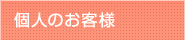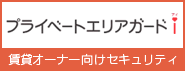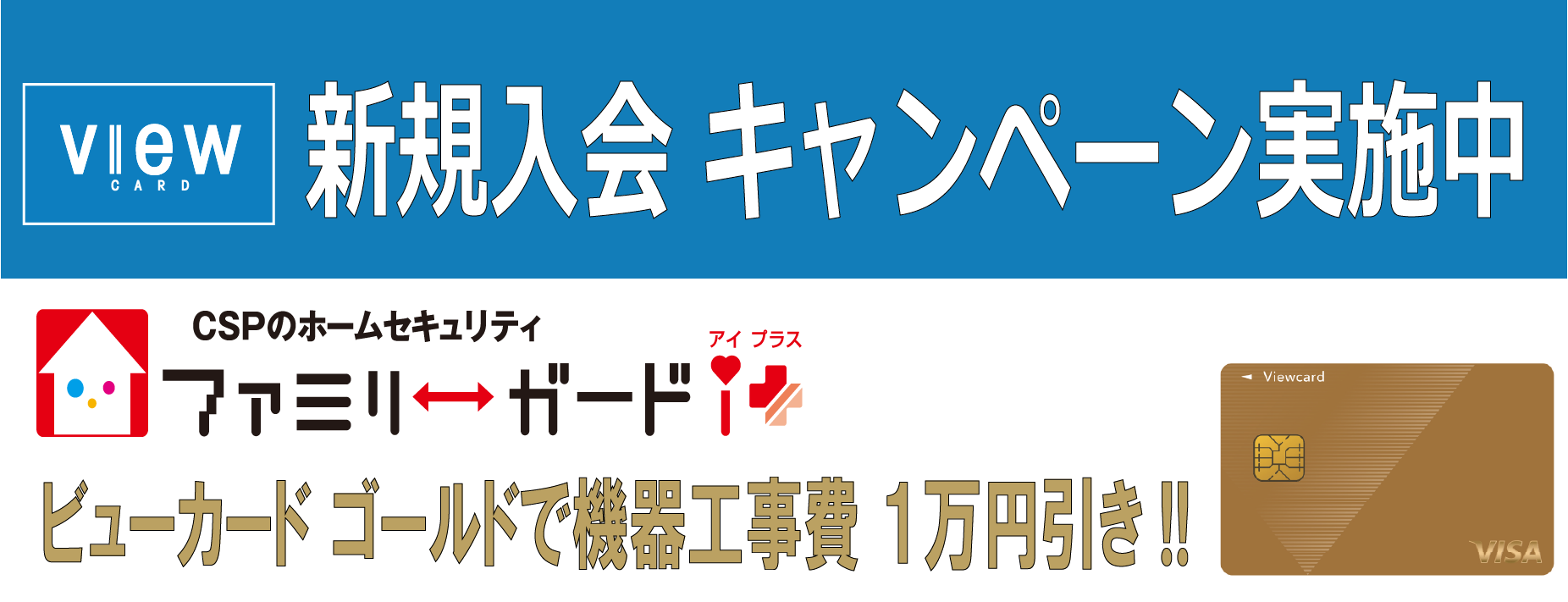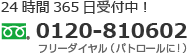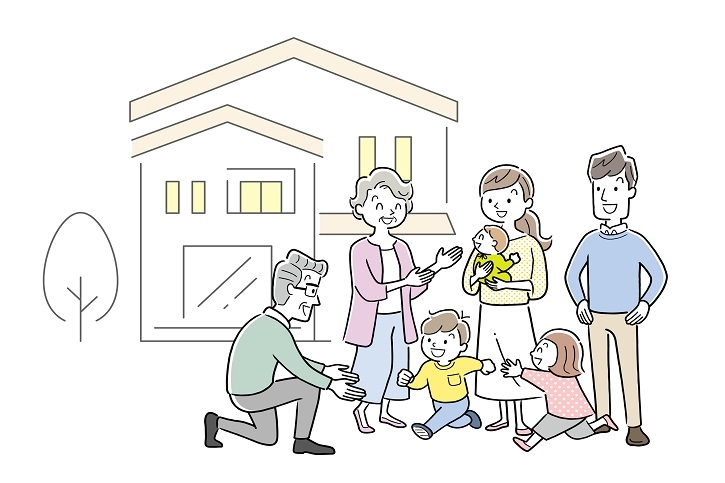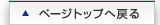CLOSE
- CSP セントラル警備保障 | 警備・防犯・防災・情報セキュリティ >
- 個人のお客様 >
- ホームセキュリティコラム >
- 親の介護が始まる前に知っておきたい準備と支援策をプロが徹底解説
親の介護が始まる前に知っておきたい準備と支援策をプロが徹底解説

親が高齢になるにつれ、介護のことが現実味を帯びてきます。「いつかは必要になる」と分かっていても、日々の忙しさに追われ、備えを後回しにしている方も多いのではないでしょうか。介護は突然始まることもあり、心の準備や情報の整理ができていないと、家族に大きな負担がのしかかります。
この記事では、親の介護に向き合うために必要な心構えや話し合いのポイント、制度やサービスの活用方法を分かりやすくご説明します。無理のない介護を続けるためのヒントとしてご活用ください。
親の変化に早く気づくことが介護の第一歩
介護が必要になるタイミングは、ある日突然訪れることがあります。特に高齢の親は、体調や行動に急な変化が現れることも少なくありません。日々の生活の中で小さな異変に気づけるよう、意識して見守ることが介護への第一歩となります。
転倒や認知症は予期せず起こる
高齢者の転倒は、骨折や寝たきりにつながる重大な事故です。床の段差やぬれた床、履きなれないスリッパなど、ちょっとした環境の変化によっても転倒は起こります。例えば、何気ない深夜のトイレ移動中に転倒し、骨折して動けなくなってしまうといったケースは珍しくありません。
また、認知症の初期症状は非常に見落とされやすく、家族であっても気づかないことがほとんどです。「同じ話を何度も繰り返すようになった」「外出先で道に迷う」「炊飯器の操作を間違える」など、ごく小さな変化から始まり、日常生活に大きな影響を及ぼす前兆となります。わずかな異変を放置すると、進行が早まる可能性があるため、些細なサインを見逃さない観察が欠かせません。
日常の小さな変化を見逃さない工夫
高齢の親の生活の変化にいち早く気づくには、観察の視点を広げることが有効です。「衣類の着替えが雑になった」「食事内容が偏るようになった」「冷蔵庫に賞味期限切れの食品が増えた」といった状況は、体力や判断力の低下を示している可能性があります。
また、ゴミ出しの頻度が減ったり、郵便物が玄関にたまっていたりと、生活リズムの乱れが見えることもあります。水道光熱費の請求書の金額が極端に変化していれば、生活の仕方自体が変わっているサインかもしれません。こうした変化を把握するためには、帰省時のチェックや、電話やビデオ通話を活用した定期的な連絡が有効です。
高齢者自身の気づきが遅れることもある
高齢者は、自身の身体機能や認知機能の低下に気づきにくい傾向があります。感覚が若い頃よりも衰えることや、認知機能の低下により自身を客観視しにくくなることが要因です。また、自分が老いてきたことを受け入れることに抵抗を感じ、症状を隠すこともあるため、周囲の配慮が重要となります。
高齢者自身が変化に気づきにくく、症状を隠してしまうこともあるからこそ、家族が客観的に変化を見つけ出す視点を持つことが求められます。あくまで否定せず、さりげなく気づきを促す会話やサポートが、本人の自尊心を保ちながら介護の受け入れへとつなげる鍵となります。
親と介護について話すための準備
介護について親と話す際は、伝え方やタイミングに工夫が必要です。感情的にならず、親の立場を尊重しながら話し合いを進めることが、信頼関係の維持にもつながります。
介護の話題は「相談」として切り出す
介護に関する話は、親にとっても子供にとってもデリケートな話題です。そのため、話を切り出す際には、「今後どうしたいか相談させてほしい」という姿勢で臨むことが大切です。「病気になったときにどうしたいか教えてほしい」「将来のために話し合っておきたい」など、前向きな理由を添えることで対話がスムーズになります。
無理に結論を出そうとせず、少しずつ会話を重ねていくことで、お互いの気持ちや希望が見えてきます。親にとっては、自分の思いを受け止めてもらえることが、介護への不安を和らげるきっかけにもなるでしょう。
本人の意向と尊厳を尊重する姿勢が大切
介護を受ける本人の意向を尊重することは、介護において極めて重要です。例えば、「施設に入りたくない」「なるべく自宅で過ごしたい」という気持ちは、生活の質に直結します。可能な限り希望を叶える形で支援を設計することが、信頼と安心につながります。
また、意向を聞き取る際は、一方的に問い詰めるのではなく、リラックスした場で「どのように暮らしていたい?」といった対話をするのが理想的です。記録を残しておくことで、いざというときに家族が判断に迷わず動けるでしょう。
家族間で役割や考えを共有しておく
介護は家族の協力なしには成り立ちません。兄弟姉妹がいる場合は、日頃から情報を共有し、役割分担について話し合っておくことがトラブル回避に役立ちます。例えば、「定期的に様子を見に行く係」「通院の付き添い係」「金銭管理を担当する係」といった役割を分け、無理なく続けられる体制を整えておくと安心です。
また、経済的な負担についても予測しておかなければなりません。介護には医療費・生活費・福祉用具などさまざまな出費が伴うため、家族で費用をどのように負担するか話し合っておく必要があります。介護離職を防ぐための選択肢として、介護サービスやテレワークなどの活用も検討しましょう。
遠距離介護で起きる課題と解決策
親と離れて暮らしていると、日常の変化や異常にすぐ気づくのが難しくなります。遠距離介護は精神的にも物理的にも制約が多く、介護に関する課題が表面化しやすい状況です。
しかし、あらかじめ起こり得る問題を想定し、適切な対策を講じることで、負担を軽減することは可能です。ここでは、遠距離介護で起きる課題と解決策をご説明します。
電話や定期連絡だけでは見えない問題もある
高齢の親と離れて暮らしていると、電話でのやり取りが主なコミュニケーション手段となりがちですが、声のトーンや話し方だけで、本当の生活状況を把握するのは容易ではありません。例えば、「元気だよ」と答えていても、実際には冷蔵庫に食材がほとんどなく食事を十分にとっていなかったり、掃除や洗濯が行き届いていなかったりと、生活の質が著しく低下していることがあります。
また、認知機能の低下が始まっていても、言葉を交わすだけでは伝わらないこともあります。ほかにも、本人が意識的に体調不良を話さない場合、電話だけのやり取りでは重大なサインを見逃してしまうリスクがあるため、直接会って様子を見る機会をできるだけ多くつくり、環境や生活状態を確認することが大切です。
定期訪問や民間サービスをうまく組み合わせる
遠距離介護を円滑に行うには、家族だけですべてを背負おうとせず、訪問介護や配食サービス、買い物代行などの民間サービスを組み合わせることが効果的です。訪問ヘルパーが定期的に自宅を訪れれば、生活の乱れにいち早く気づけるだけでなく、安否確認の役割も果たせます。
また、ケアマネージャーや地域包括支援センターと連携をとっておくことで、要介護認定や介護保険サービスの利用もスムーズに行えます。地域の見守りボランティアや配食サービスの利用は、第三者の目を増やす意味でも有効です。親の住まいのある地域にどのような支援制度や民間サービスがあるのかを事前に調べ、必要に応じて活用しましょう。
遠くにいても安心できる仕組みが必要
仕事や家庭の都合で頻繁に実家へ帰ることができない場合は、安否確認サービスや緊急通報サービスを導入することで安心につながります。高齢者がボタンを押すだけで緊急時に通報できるシステムや、センサーが一定時間高齢者の動きがないことを検知して通報するシステムなど、技術の進歩により多様なサービスが登場しています。
また、スマートフォンを活用した見守りアプリを導入すれば、家族が遠隔で状況を確認でき、万が一のときにも対応できます。
介護に限界を感じたときの対応策
介護を続けていく中で、限界を感じる瞬間は誰にでも訪れます。特に、一人で介護を担っていると、心身ともに大きな負担を抱え込みやすくなります。無理を感じる前に、適切な支援やサービスを利用しましょう。
肉体的にも精神的にも「疲れ」はサイン
介護を担っていると、自分の体調や気分の変化に気づきにくくなります。慢性的な睡眠不足や食欲の低下、気分の落ち込みなどは、ストレスが積み重なっているサインです。
感情が不安定になり、介護される側に対して冷たくなってしまうことがあるなら、無理をしている証拠かもしれません。そのような状態になったら、小休止をとったり、話を聞いてくれる相手に相談したりと、自分の気持ちを整えることが大切です。
自治体や民間の相談窓口を活用する
介護の悩みは身近な人に話しづらいと感じることもありますが、外部の相談窓口を活用すれば、客観的な視点から助言をもらうことが可能です。例えば、地域包括支援センターでは、介護に関する悩みや制度の利用方法などを、専門の相談員に無料で相談できます。
他にも、NPO法人が運営する電話相談や、介護経験者による家族会なども頼れる存在です。困ったときに話を聞いてくれる相手がいることで、気持ちの整理がしやすくなります。
介護が苦しいときに頼ってよいサービス
介護を少しの間、他人に委ねることは、決して悪いことではありません。むしろ、継続して介護を続けていくには、休息をとる時間が欠かせません。介護保険を利用すれば、短期間の入所ができるショートステイや訪問介護、訪問看護などのサービスが使えます。また、最近では高齢者の見守りサービスを展開している民間企業も多く、カメラやセンサーでの見守りや、緊急時に駆けつけてくれる仕組みを利用する家庭も増えています。
どのサービスを使うか迷った場合も、前述の相談窓口で情報提供や紹介を受けることが可能です。一人で抱え込まず、適切にサービスを取り入れることで、介護者の心と体に余裕が生まれます。疲れを感じたときには「頼ることは前向きな選択」と考えて、できることから取り入れていきましょう。
離れて暮らす親を支える見守りサービスという選択
高齢者の見守りを目的としたサービスには、多くの選択肢があります。異常を検知して知らせる機器や、緊急時に駆けつける体制などが整っており、離れて暮らす家族も日常の安全・安心を支えることが可能です。
緊急ボタンで駆けつける仕組み
CSPが提供するシニア向け見守りサービス「見守りハピネス」は、異常が起きた際に本人が緊急ボタンを押すだけで、自動的に通報される仕組みです。転倒や急な体調不良などの緊急時にもすぐに通報が可能で、パトロール員が駆けつけて対応します。
夜間の急変にも備えられる安心感
一人暮らしの高齢者にとって、夜間など周囲に助けを求めにくい時間帯の対応は重要です。「見守りハピネス」では、24時間365日の見守り体制が整っており、万が一の異変も見逃さず対応できます。
日常生活の中でいつ何が起きても、頼ることができる支援体制があるという点は、本人にとっても家族にとっても心強い支えになります。
見守られている安心感が自立も支える
見守りサービスは、高齢者の「自立」を妨げるものではありません。むしろ、「何かあっても助けてもらえる」という心のゆとりがあるからこそ、高齢者自身も自信を持って暮らしを継続できます。
転倒や急な体調不良などの緊急時に、緊急ボタンを押すだけで自動的に通報される緊急通報サービスや、自宅に設置されたセンサーが一定時間高齢者の動きを検知しない場合に、異常が起こったと判断して自動で通報されるライフリズムサービスが、心理的な安定を支える役割を果たします。
まとめ
親の介護は、思いがけないタイミングで始まることもあります。だからこそ、家族で話し合い、制度やサービスの情報を整理しておくことが重要です。同居介護や遠距離介護にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、各ご家庭に最適な方法を選ぶことで、家族の心身の負担を軽減できるでしょう。また、介護を一人で抱え込まず、外部の支援を活用することも大切です。
離れて暮らす親の安全を見守りたいという方には、緊急時の対応体制が整った、CSPが提供するシニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の利用も、安心を支える一つの選択肢になるでしょう。
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の詳細ページはこちら↓
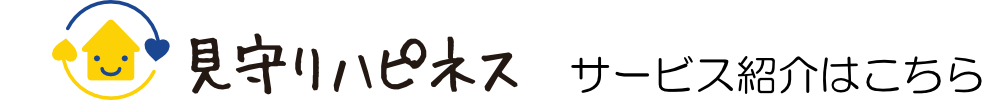
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ+」
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の資料請求やお見積り依頼はこちら↓
おすすめ記事