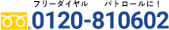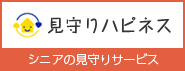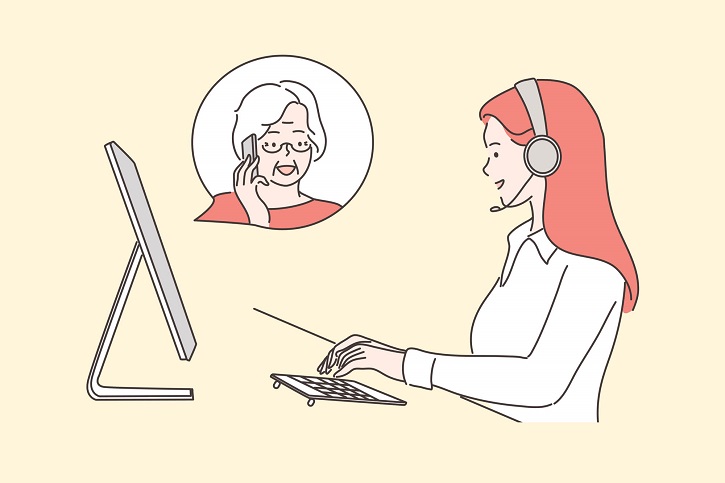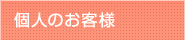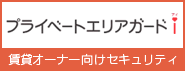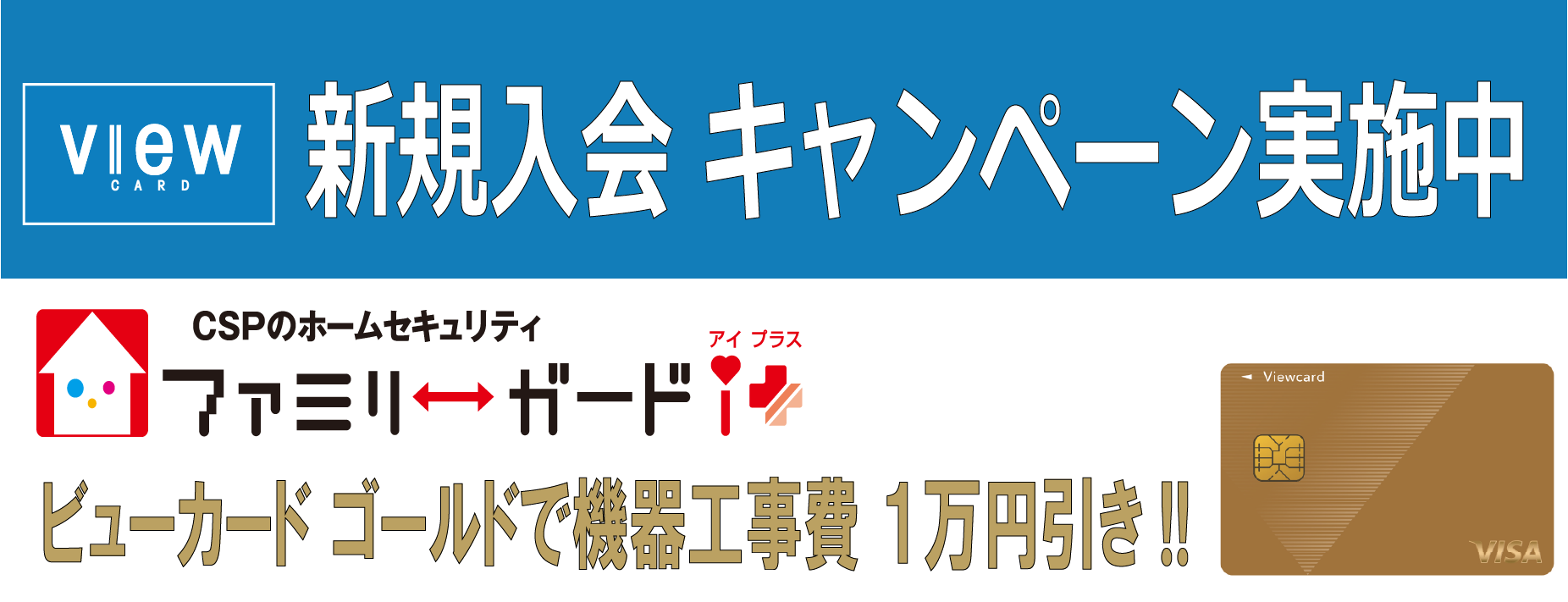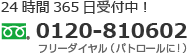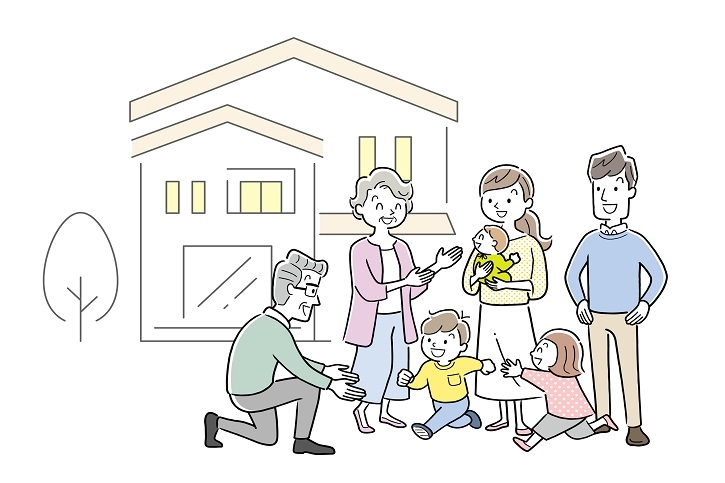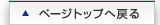CLOSE
- CSP セントラル警備保障 | 警備・防犯・防災・情報セキュリティ >
- 個人のお客様 >
- ホームセキュリティコラム >
- 介護保険の認定調査で正しく評価されるためのコツとは?準備と対応を解説
介護保険の認定調査で正しく評価されるためのコツとは?準備と対応を解説
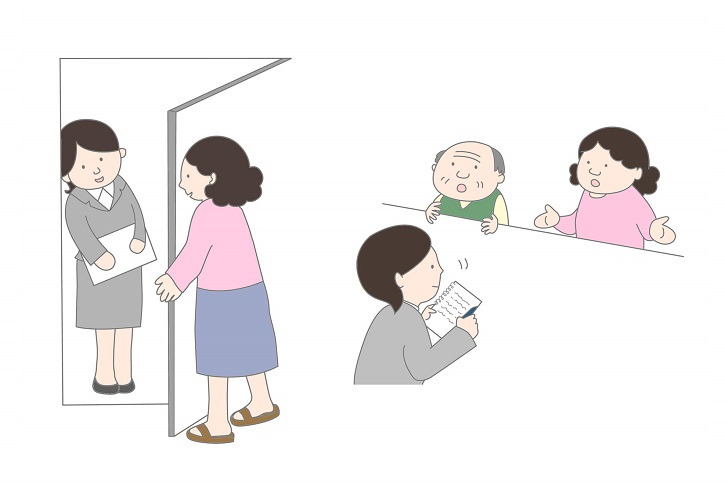
介護保険を利用するには、「要介護認定」を受ける必要があり、その判断材料として「認定調査」という訪問調査が行われます。調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態や日常生活の様子を確認しますが、実際よりも軽い介護度で判定されてしまうと、必要な支援を十分に受けられないこともあります。本人の状態を正しく伝えるには、事前の準備や家族の協力がとても重要です。
この記事では、認定調査で押さえておきたい伝え方のコツや注意点を分かりやすくご説明します。
- 介護保険の認定調査とは?
- 認定調査で正しい評価を受けるために押さえておきたいコツ
- 介護サービスでは補えない時間を支える「見守り」の重要性とは
- 一人の時間も安心して過ごせる「見守りハピネス」が支える高齢者の暮らし
- まとめ
介護保険の認定調査とは?
介護サービスの利用には、本人の心身の状態を把握するための「認定調査」が必要です。調査結果は要介護度の判定に直結し、受けられる支援内容に大きく影響します。
介護サービスを利用するためのスタートライン
介護サービスを受けるための最初のステップは、認定調査です。介護保険によるサービスを受けるには、まず自治体に要介護認定の申請を行い、審査を経て認定を受ける必要があります。
認定調査は、要介護度を判断するための重要なプロセスです。調査の結果によって受けられるサービスの内容が変わるため、正確な評価を受けられるかどうかが、支援内容に大きく影響します。
認定調査の流れと調査項目
介護保険の申請後、本人の状態を確認するために、自治体の職員や委託を受けた調査員が、自宅や入所施設を訪問します。訪問調査では、本人と家族に対して聞き取りを行いながら、実際の動作や表情、生活環境などを観察・記録します。
調査項目には主に以下のような内容が含まれます。
| 身体機能や起居動作 | 立ち上がり、歩行、寝返りなど |
|---|---|
| 生活機能 | 食事、排泄、入浴、着替えなどの身の回りの動作 |
| 認知機能 | 日時や場所の認識、意思の伝達、記憶など |
| 精神・行動面の状態 | 不安、幻覚、徘徊、暴言・暴力の有無など |
| 社会生活への適応 | 買い物、金銭管理、人との関わりなど |
| 医療的な対応の必要性 | ストーマの処置、気管切開の処置、医療機器の使用など |
調査員が聞き取りした情報は報告書としてまとめられ、一次判定でコンピュータ判定にかけられた後、主治医の意見書や介護認定審査会による審査を経て、要介護度が決定されます。調査は限られた時間で行われるため、日常生活の実態を正確に伝えることが、適切な介護度の認定につながります。
認定調査で正しい評価を受けるために押さえておきたいコツ
認定調査では、限られた時間の中で状態を伝える必要があるため、事前の準備や伝え方の工夫が欠かせません。正しく評価されるために、押さえておきたいポイントをご紹介します。
調査内容を理解しておく
調査当日は、短時間の中で多くの質問に答えなければなりません。そのため、あらかじめ調査項目の内容を把握しておくことで、心に余裕が生まれ、落ち着いて受け答えができるようになります。どのような視点で評価されるかを知ることで、実際の生活の困難さをより的確に伝えられるでしょう。
実際の生活で困っていることを正直に伝える
調査の場では、「迷惑をかけたくない」「できないと思われたくない」という気持ちから、本人が実際よりも良く見せようとすることがあります。しかし、正確な支援につなげるためには、日常生活で困っている点を正直に伝えることが欠かせません。食事・排泄・入浴・移動など、日常生活でどのような困難があるのかを、具体的に伝えることが大切です。
家族が同席して補足説明を行う
本人が緊張してうまく話せない場合や、認知症の影響で記憶があいまいな場合は、日常生活をよく知る家族が立ち会い、必要に応じて補足説明を行いましょう。転倒歴や介助が必要な場面などを、第三者の目線で伝えることで、より実態に即した評価を得やすくなります。
「できる日」と「できない日」の差を説明する
高齢者の体調や精神状態は、日によって大きく変化することがあります。そのため、日によってできること・できないことに差が出る高齢者も少なくありません。調査員には、普段の体調やできること・できないことの割合、支援が必要な頻度などを具体的に伝えることが大切です。
持病・服薬・認知症の症状も伝える
心身の状態を正しく評価してもらうには、これまでにかかった病気や現在の服薬状況、認知症の症状なども詳しく伝える必要があります。調査員が介護の必要度を判断する上で重要な要素になるため、あらかじめ診断名や通院状況、服薬内容を整理しておくと、スムーズに説明できます。
評価に納得できないときは不服申立ても視野に入れる
介護度が実際の状態よりも軽く判定されたと感じた場合には、不服申立てを行うことが可能です。不服申立ては、結果通知を受け取った翌日から3カ月以内に申請を行う必要があります。本人の生活の質を守るためにも、納得できるまで制度を活用しましょう。
介護サービスでは補えない時間を支える「見守り」の重要性とは
介護サービスには対応できる時間や内容に限りがあるため、すべての不安をカバーできません。そのようなときに役立つのが「見守り」の支援です。
認定調査では見えない「生活の不安」もある
訪問による調査は一時的なものであり、日常生活の実態をすべて把握するのは難しいのが現状です。認定調査の結果だけでは判断しきれない支援の必要性もあり、介護サービスだけでは不安が残ることもあります。
一人暮らしや家族の留守を補う見守りの役割
高齢者が一人で暮らしている場合や、家族が日中仕事で留守がちな家庭では、急な体調の変化や事故などにすぐ対応できないことが、大きな不安につながります。このような状況では、見守りサービスの導入が心強い支えになります。見守りサービスを導入することで、目の届かない時間帯も安心して過ごせる環境を整えることが可能です。
一人の時間も安心して過ごせる「見守りハピネス」が支える高齢者の暮らし
一人で過ごす時間にも不安を感じずに生活できるよう、「見守りハピネス」は高齢者の安全と安心をサポートします。
ボタンひとつで緊急通報と駆けつけ対応
「見守りハピネス」は、体調の急変や転倒など、万が一のときにボタンを押すだけでCSPの指令センターに通報できる緊急通報サービスです。パトロール員が必要に応じて自宅へ駆けつけます。夜間や休日も含めた24時間365日の対応により、一人暮らしの高齢者でも安心して暮らせる環境が整うでしょう。
高齢者でも使いやすいシンプル設計
通報機器は操作が非常にシンプルで、機械に不慣れな高齢者でも扱いやすいように配慮されています。固定型と携帯型があり、寝室に固定型を設置しつつ携帯型を常に首に掛けておくなど、状況に応じて使い分けることも可能です。必要なときに助けを呼べる環境を整えることで、本人にも家族にも安心を届けます。
離れて暮らす家族にも連絡
通報があった場合、事前に登録された家族にも連絡が入ります。離れて暮らす家族も状況を把握しやすく、日常的な不安や「何かあったときに気づけるだろうか」という心配を軽減できるでしょう。
まとめ
介護保険の認定調査では、限られた時間の中で本人の状態を正しく伝えることが求められます。しかし、一人暮らしの高齢者や家族が留守の時間帯など、一人で過ごしているときの困りごとは調査では見えにくく、支援の必要性が正確に伝わらないこともあります。
CSPのシニア向け見守りサービス「見守りハピネス」は、緊急時にボタンを押すだけで通報でき、必要に応じてパトロール員が駆けつけるサービスです。高齢者が自宅で安心して暮らし続けるための備えとして、「見守りハピネス」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の詳細ページはこちら↓
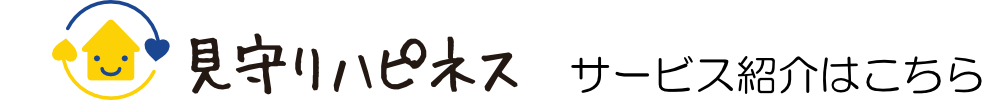
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ+」
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の資料請求やお見積り依頼はこちら↓
おすすめ記事