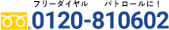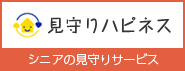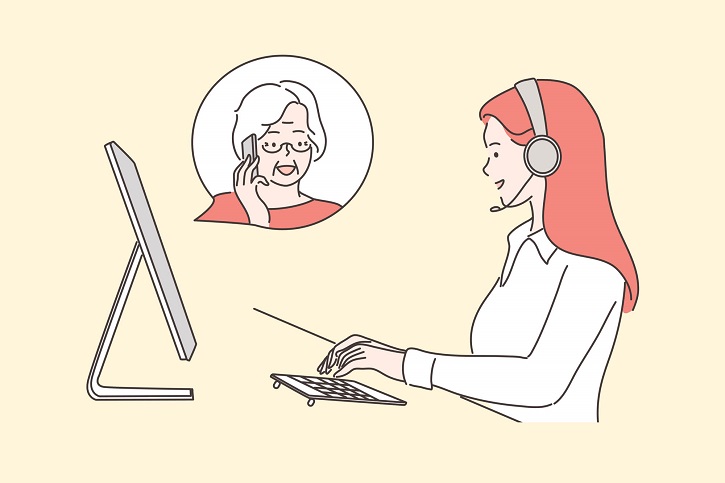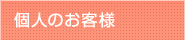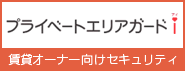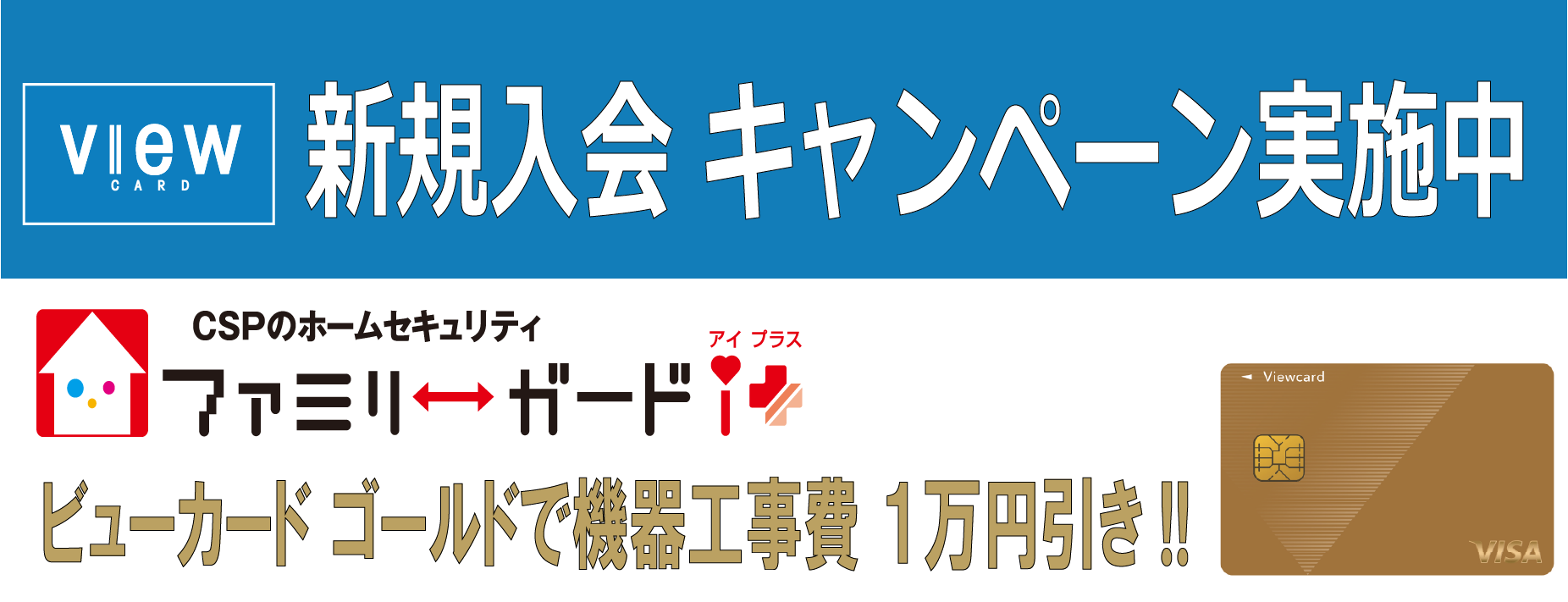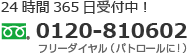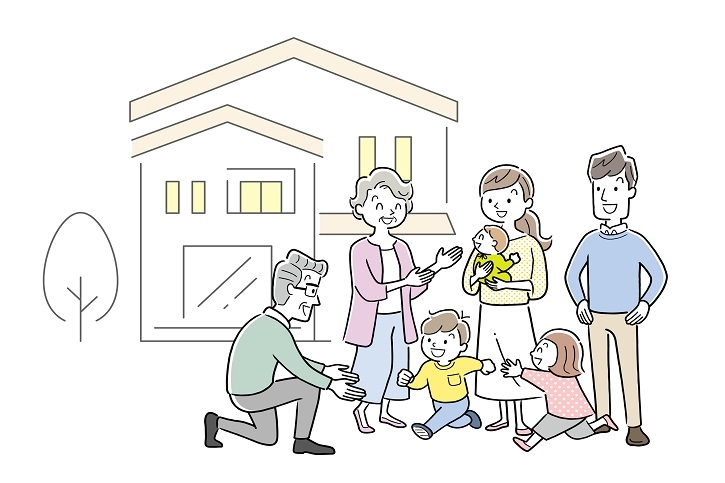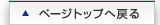CLOSE
- CSP セントラル警備保障 | 警備・防犯・防災・情報セキュリティ >
- 個人のお客様 >
- ホームセキュリティコラム >
- 要介護5とは?他の介護度との違いと利用可能なサービスや給付金を解説
要介護5とは?他の介護度との違いと利用可能なサービスや給付金を解説

「要介護5」と認定された方は、日常生活を送る上で、常に介護を必要とする状態です。本人だけでなく、介護にあたる家族にとっても、負担は決して小さくありません。
この記事では、要介護5とはどのような状態なのか、認定基準や他の介護度との違い、利用できる介護保険サービスについて詳しくご説明します。さらに、在宅介護ができるかどうかや、気になる給付金や費用についても触れますので、ぜひ参考にしてください。
- 要介護5とは
- 要介護5の方が利用できる介護保険サービス
- 要介護5の方を自宅で介護できる?
- 要介護5の方が受けられる給付金
- 要介護5の方の介護にかかる費用とケアプランの事例
- 離れて暮らす家族を見守るなら「見守りハピネス」がおすすめ
- まとめ
要介護5とは
高齢の家族と同居している方なら、「要介護5」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。介護保険制度における最も重い区分である要介護5は、本人や家族にとって、日々の生活に大きな影響を与えるものです。
ここでは、要介護5がどのような状態を指すのかを、認定基準や他の介護度との違いと併せてご説明します。
要介護5の状態
要介護5の状態とは、日常生活において全面的な介護が必要とされる状態のことを指します。具体的には、要介護認定で基準時間が110分以上とされる、またはそれに相当する状況にある方が対象となります。
日常生活のほぼすべての場面で介護が必要となるため、身体的・精神的な面で総合的なサポートが求められます。具体的には、食事や排泄、入浴、着替えといった基本的な生活動作を自力で行うことが困難なため、家族や専門の介護職員による支援が不可欠です。
要介護5に認定される方の多くは、一日のほとんどを寝たきりの状態で過ごします。筋力の低下や関節の硬直によって移動や寝返りが難しく、さらに認知機能の低下や精神疾患により、意思疎通が困難なケースも少なくありません。
そのため、全面的な介助と見守りが必要で、介護者の負担も非常に大きくなります。
要介護5の認定基準
介護保険制度における要介護度は、厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」をもとに、要支援1・要支援2、要介護1~要介護5の7つの段階に区分されています。介護が必要な方にどれくらいの介護サービスを提供する必要があるか、その目安となる時間が要介護度別に定められています。
| 区分 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 |
| 要介護1 | 32分以上50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
一日に必要な介護の時間が110分以上と判定されると、要介護5に認定される可能性が高いです。また、寝たきりでなくても、重度の認知症により理解力が低下し、意思疎通が難しい場合には、要介護5に認定されることもあります。
加えて、介護認定を受けるまでには、さまざまな手続きが必要です。介護認定を受ける手順は以下のようになります。
step1.地域包括支援センターに相談する
step2.必要書類をそろえて要介護認定の申請を行う
step3.ケアマネジャーや市の職員が訪問して本人の状態を調査する
step4.認定結果が通知されたら居宅介護支援事業所へ連絡する
step5.ケアマネジャーがケアプランを作成する
step6.介護サービスを提供する事業所と利用の調整を行う
他の介護度との違い
| 区分 | 状態 |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活は1人で送れるが、介護予防のための支援が必要 |
| 要支援2 | 動作能力が低下しているため支援が必要だが、状態の維持・改善の可能性が高い |
| 要介護1 | 日常生活はほぼ1人で送れるが、入浴や排泄などの部分的な介助が必要 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加えて、歩行や食事などの日常生活動作の介助が必要 |
| 要介護3 | 日常生活のほとんどで介助が必要 |
| 要介護4 | さらなる動作能力の低下により、要介護3の状態に加えて、すべての日常生活の介助が必要 |
| 要介護5 | 要介護4の状態より動作能力が低下し、全面的な介助が必要 |
介護度によって状態は大きく異なります。例えば、要介護4の方は、身体の機能が低下しているだけでなく、思考力や理解力も衰えていますが、介助があれば座ったり会話したりすることが可能です。一方で要介護5の方は、身体機能がさらに低下している上に認知機能も低下しているため、一日のほとんどを寝たきりで過ごし、意思疎通が非常に難しい状態です。
要介護5の方が利用できる介護保険サービス
要介護5の方は、日常生活の全般で全面的な支援が必要となる状態です。そのため、介護保険のサービスを最大限に活用することが、本人と家族の生活の質を保つ上で非常に重要です。
ここでは、要介護5の方が利用できるさまざまな介護保険サービスをご紹介します。
自宅で利用できるサービス
自宅で生活を続けながら介護サービスを利用したい場合、以下のようなサービスが利用可能です。
訪問介護
介護福祉士やホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排泄・着替えの介助などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・買い物などの生活援助を行います。
訪問入浴介護
介護職員や看護師が専用の浴槽を持参し、自宅で入浴介助を行うサービスです。
訪問看護
看護師や保健師が自宅を訪問し、病状の観察、点滴や床ずれケアなどの医療処置、服薬管理、ターミナルケア、療養上の相談・指導などを行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、身体機能の維持・向上、日常生活動作の改善などを目的としたリハビリテーションを行うサービスです。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
夜間対応型訪問介護
夜間(おおむね18時から翌朝8時まで)に、介護福祉士やホームヘルパーが自宅を訪問し、介護サービスを行います。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
24時間体制で介護職員と看護師が連携し、定期的な訪問と利用者からの通報に対応して、訪問介護や訪問看護を行うサービスです。
施設に通って利用できるサービス
日中、施設に通ってサービスを利用したい場合、以下のようなサービスがあります。
通所介護(デイサービス)
施設に通い、食事や入浴、レクリエーション、機能訓練などを受けます。
通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による専門的なリハビリテーションを受けます。
地域密着型通所介護
地域に密着した小規模な定員の施設で、介護サービスを受けます。
療養通所介護
医療機関や訪問看護ステーションなどに併設された、重度の要介護者や医療的ケアが必要な方が利用できる通所介護です。痰の吸引や経管栄養などを、医療的な専門知識を持ったスタッフが行います。
認知症対応型通所介護
認知症の方を対象とした通所介護で、認知症の症状に合わせたケアやレクリエーションを提供します。
訪問・通い・宿泊を組み合わせて利用できるサービス
自宅での生活を軸に、必要に応じて施設でのサービスも利用したい場合に有効なのが、以下のサービスです。
小規模多機能型居宅介護
通い(デイサービス)を中心に、訪問介護や泊まり(ショートステイ)を組み合わせて利用できるサービスです。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
小規模多機能型居宅介護に、訪問看護の機能が加わったサービスです。医療的な管理が必要な方にとって、自宅での生活を継続しながら、必要に応じて医療的なケアも受けられるため、非常に心強いでしょう。
短期間のみ施設に宿泊して利用できるサービス
家族の介護負担軽減や一時的な理由で、自宅での介護が困難な場合に利用できます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、食事や入浴、排泄などの介護サービスを受けます。
短期入所療養介護
介護老人保健施設や介護医療院などに短期間入所し、医療的なケアやリハビリテーションを受けます。
施設に入居して利用できるサービス
自宅での生活が困難になった場合や、24時間体制での介護が必要な場合に検討されるのが、施設への入居です。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入居し、生活全般の介護サービスを受けられます。原則、終身にわたって利用可能で、24時間体制での手厚い介護が受けられます。
介護老人保健施設(老健)
病状が安定し、病院での治療が終了した方が、在宅復帰を目指してリハビリテーションや医療ケアを受けながら生活する施設です。医療的なケアが必要な方が、集中的なリハビリテーションを受け、在宅復帰を目指す場合などに利用します。
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど)
特定施設として指定された有料老人ホームや軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入居し、介護サービスや生活支援サービスを受けます。本人の状態や家族の希望に合わせて選択します。
介護医療院
長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を受け入れる施設です。医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えています。医療依存度の高い方にとって、長期的な医療ケアと生活支援が一体的に受けられる新しい選択肢です。
地域密着型のサービス
住み慣れた地域で、地域住民との交流を保ちながらサービスを利用したい場合に有効です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が共同生活を送る住居で、専門的なケアを受けながら、自立した生活を送れるよう支援します。重度の認知症を伴う方でも、少人数での共同生活のため、落ち着いた環境できめ細やかなケアを受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員29名以下の小規模な介護老人福祉施設で、地域に住む要介護者が入居し、食事や入浴などの日常生活の支援の他、機能訓練や療養上の介護サービスを受けます。
地域密着型特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護のうち、定員29名以下の小規模な施設で提供されるサービスです。小規模な有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、地域密着型のサービスを受けたい方に適しています。
福祉用具で利用できるサービス
自宅での生活をより安全で快適にするために、福祉用具の利用も検討しましょう。
福祉用具貸与
車椅子や特殊寝台、床ずれ防止用具、手すり、歩行器、移動用リフトなど、さまざまな福祉用具をレンタルできます。要介護5の方の場合、特殊寝台や車椅子など、日常生活を支える上で欠かせない福祉用具が多く、レンタルすることで、本人の快適性の向上と介護者の負担軽減につながります。
特定福祉用具販売
入浴補助用具や排泄用具、簡易浴槽など、貸与になじまない性質の福祉用具を、費用の補助を受けて購入できます。ポータブルトイレや入浴用の椅子など、衛生管理や排泄介助に不可欠な福祉用具の購入が該当します。
要介護5の方を自宅で介護できる?
要介護5と認定された方を、自宅で介護できるのでしょうか? 身体機能や認知機能が著しく低下し、日常生活のほぼ全般にわたって全面的な介助が必要となる要介護5の状態では、在宅介護には多くの課題が伴います。しかし、適切な準備と支援があれば、住み慣れた自宅での生活を継続することも可能です。
ここでは、要介護5の方の在宅介護の可能性や課題と併せて、在宅介護と施設介護それぞれのメリット・デメリットをご説明します。
要介護5でも自宅で介護できるのか?
要介護5の方の在宅介護は、多くの課題が伴いますが、利用できるサービスや地域の支援を最大限に活用することで実現可能です。
要介護5の状態では、寝たきりであったり、意思疎通が困難であったり、誤嚥や床ずれのリスクが高かったりと、専門的な知識と技術を要する介護が日常的に必要となります。そのため、家族だけで介護をすべて担うことは非常に困難であり、介護する家族の身体的・精神的な負担は非常に大きくなることを理解しておかなければなりません。
しかし、前述したように、訪問介護や訪問看護、訪問リハビリテーションや短期入所サービスなど、さまざまな介護保険サービスを組み合わせることで、在宅での生活を支えることは可能です。
重要なのは、無理のない介護体制を構築することです。介護保険サービスや地域の支援を積極的に利用し、家族だけで抱え込まず、外部の力を借りることが、在宅介護を継続するための鍵となります。
在宅介護のメリット
自宅での介護には主に3つのメリットがあります。
住み慣れた環境で生活できる
長年過ごしてきた自宅は、本人にとって最も安心できる場所です。環境の変化によるストレスが少なく、慣れた空間で日々の生活を送れます。
家族と過ごせる
毎日、家族と共に時間を過ごせることは、本人にとっても家族にとっても、かけがえのない喜びです。精神的な安定につながり、認知機能の低下抑制にも良い影響を与えることがあります。
個別にケアできる
施設では集団でのケアが中心となることが多いですが、在宅介護では本人の生活リズムや好みに合わせて、きめ細かく個別のケアを提供できます。食事の時間や入浴のタイミングなど、柔軟に対応することが可能です。
在宅介護のデメリット
在宅介護にはメリットがある一方、無視できないデメリットも存在します。
介護の負担が大きい
要介護5は、日常生活のほぼすべてに介助が必要な状態です。食事や入浴、排泄や体位変換など、24時間体制での介護が求められるため、介護者の身体的・精神的な負担は計り知れません。
医療ケアに限界がある
自宅では、高度な医療機器の設置や専門的な医療処置を、常時行うことは困難です。点滴や床ずれケア、痰の吸引など、医療的な管理が必要な場合でも、対応が難しい場合があります。
緊急時の対応が困難
急な体調の変化や転倒など、予期せぬ事態が発生した場合、介護者だけで迅速かつ適切に対応するのは難しいでしょう。救急車を呼ぶ判断や医療機関への搬送など、介護者の負担は大きくなります。
在宅介護に必要な準備
要介護5の方の在宅介護を検討する際には、入念な準備が不可欠です。
住環境の整備
車椅子での移動を考慮した段差の解消や手すりの設置、滑りにくい床材への変更、ポータブルトイレの設置など、本人の状態に合わせた住環境の改修が必要です。福祉用具の導入も積極的に検討しましょう。
介護体制の構築
家族だけですべてを抱え込まず、訪問介護や訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所などの介護保険サービスを積極的に利用し、介護のプロの力を借りることが重要です。
情報収集
介護保険制度や利用できるサービス、地域の支援体制について、積極的に情報収集を行いましょう。地域包括支援センターやケアマネジャーに相談することで、最適なサービスの組み合わせを提案してくれます。
負担が大きい場合は施設での介護も検討しよう
在宅介護にはメリットがある一方で、要介護5の方の介護は、家族にとって非常に大きな負担となる現実があります。もし、介護疲れを感じたり、介護者が体調を崩してしまったりするようであれば、無理に在宅介護を継続するのではなく、施設での介護を検討することをおすすめします。
施設介護のメリット
施設での介護には、在宅介護では得られない多くのメリットがあります。
専門的なケアを24時間365日受けられる
施設には、介護福祉士など専門のスタッフが24時間常駐しています。必要な身体介護を必要なときにいつでも受けられますし、施設によっては看護師も常駐しており、医療的なケアも常に受けることが可能です。そのため、家族の夜間の不安も軽減されます。
設備と環境が整っている
多くの介護施設では、入浴設備やリハビリテーション設備、緊急コールシステムなど、要介護者が安全かつ快適に過ごせるための設備が整っています。バリアフリー設計はもちろんのこと、レクリエーションを行うための共有スペースなども充実しています。
緊急時に迅速に対応できる
施設では、入居者の急な体調変化や転倒など、緊急事態が発生した場合でも、介護職員と看護師や医師との連携により迅速な対応が可能です。医療機関への搬送などもスムーズに行われます。
家族の介護負担を軽減できる
施設に預けることで、家族は日々の介護から解放され、自分の時間や休息を確保できます。面会は自由にできるため、精神的なゆとりを持って本人と接することが可能です。
他の入居者との交流の機会がある
施設には多くの方が生活しており、レクリエーションやイベントなどを通じて、他の入居者と交流する機会があります。
施設介護のデメリット
多くのメリットがある施設介護ですが、当然ながらデメリットも存在します。
費用がかかる
施設の種類やサービス内容によって費用は大きく異なりますが、入居一時金や月額費用が発生します。特に、有料老人ホームなどでは高額になるケースもあるため、経済的な負担は大きくなるでしょう。
個人の自由が制限される
施設では、ある程度の集団生活のルールやスケジュールが存在するため、自宅にいるときと比べて、個人の自由が制限される場合があります。
環境の変化によるストレスを感じることがある
住み慣れた自宅から施設へ移ることで、環境の変化に戸惑い、精神的なストレスを感じる方も少なくありません。特に、認知症の方の場合は、症状が悪化する可能性も考慮する必要があります。
入所するまでの競争が激しい
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)など、費用が比較的安価で人気の高い施設は、入所待ちが長期間にわたるケースも多いでしょう。
要介護5の方が受けられる給付金
要介護5の方の介護には、介護サービスや福祉用具の利用など、多くの費用が発生しますが、介護保険や各種支援制度を活用することで、費用の負担を軽減することが可能です。
ここでは、要介護5の方が受けられる主な給付金や費用助成制度をご紹介します。
高額介護サービス費
1カ月間に支払った介護サービス費の利用者負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険の両方を利用し、年間の自己負担額が高額になった場合に、所得区分に応じた上限額を超えた部分が払い戻される制度です。
特定入所者介護サービス費
低所得の要介護者が、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設に入所した場合に、食費と居住費の一部が軽減される制度です。
医療費控除
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担が軽減される制度です。介護保険サービスの利用者負担額やおむつ代なども、医療費控除の対象となる場合があります。
障害者控除
身体障害者手帳などがなくても、要介護認定を受けて「障害者控除対象者認定書」が発行されている方は、障害者控除が適用される場合があります。
介護休業給付金
家族を介護するために介護休業を取得する場合、条件を満たせば給付金を受け取れます。支給額は賃金の一定割合です。
福祉用具購入費
貸与になじまない入浴補助用具や簡易浴槽などの特定福祉用具を購入した場合に、購入費の一部が支給される制度です。毎月の利用上限額とは別に、1年間につき上限10万円で購入費の一部が支給されます。
住宅改修費用
自宅をバリアフリー化するなど、介護のための住宅改修を行った場合に、費用の一部が支給される制度です。手すりの取り付けや段差の解消、滑り防止のための床材変更などが対象となります。
家族介護慰労金
自治体によっては、在宅で要介護度の高い高齢者を介護している家族に対して、介護の負担を慰労する目的で給付金を支給しています。
“介護保険の要介護4または5の要介護者を介護する家族などの方で、要介護者が1年間介護保険制度で提供されるサービスを利用していないなど、要件を満たした方に年額10万円を支給します。”
引用:大阪市「家族介護慰労金」
支給要件や金額は自治体によって異なりますので、住んでいる自治体に確認しましょう
自治体独自の給付金制度
国の制度の他にも、各自治体が高齢者や介護者を支援するために、独自の給付金や助成金制度を設けている場合があります。例えば、おむつ代の助成や緊急通報システムの設置費用の助成など、多岐にわたります。
“失禁状態で2か月以上継続しておむつを使用している、ねたきり等で、要介護3~5に認定された方に、紙おむつを支給します(1か月500円の利用者負担金あり)。”
住んでいる自治体や地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。
要介護5の方の介護にかかる費用とケアプランの事例
要介護5の介護費用は、多岐にわたるサービスを利用するため、高額になりがちです。在宅介護と施設介護では費用項目や金額が異なり、個別のケアプランによっても最終的な費用は変動します。
ここでは、要介護5の方の介護費用の内訳と、在宅介護・施設介護それぞれのケアプランの事例をご紹介します。
在宅介護
在宅介護では、次のような項目で費用が発生します。
介護保険サービスの自己負担額
訪問介護や訪問看護などのサービス利用料として、収入に応じて1~3割を自己負担します。
福祉用具のレンタル代
特殊寝台や車椅子など、介護保険でレンタルできる福祉用具の自己負担額です。
おむつ代
排泄ケアに必要なおむつやパッドなどの消耗品費用が必要です。医療費控除の対象となる場合もあります。
食費
食事にかかる費用には、介護食や栄養補助食品なども含まれます。
水道光熱費
空調の使用や介護機器の稼働により、増加することが多いです。
医療費
医療的なケアが必要な場合、訪問診療や薬代などが追加されます。
施設介護
施設に入居する場合は、次のような費用が必要になります。ただし、施設の種類やサービスの内容によって、費用は大きく異なります。
居住費・管理費
施設の家賃や共益費に相当する費用です。有料老人ホームなどでは、初期費用として入居一時金が必要な場合もあります。
食費
施設で提供される食事にかかる費用です。
介護サービス費
施設が提供する介護サービスにかかる費用で、介護保険の自己負担分(原則1割、所得に応じて2~3割)と、介護保険適用外のサービス費用が含まれます。
おむつ代
施設で提供されるおむつやパッドなどの消耗品費用がかかります。
水道光熱費
基本的には施設利用料に含まれることが多いですが、別途徴収される場合もあります。
医療費
施設内で受けられる医療行為以外の、通院や入院にかかる医療費などが必要です。
ケアプラン事例
在宅介護
Aさんの場合(要介護5、寝たきり、経管栄養、奥様が主な介護者)
| サービス内容 | 利用回数(1カ月あたり) | 費用(自己負担1割) |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 20回 | 6,780円 |
| 訪問入浴介護 | 4回 | 5,744円 |
| 訪問看護 | 8回 | 4,696円 |
| 訪問リハビリテーション | 8回 | 2,656円 |
| 通所介護(デイサービス) | 8回 | 9,336円 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 1回 | 1,120円 |
| 福祉用具貸与 | - | 2,428円 |
| 1カ月の介護保険サービス自己負担額合計(目安) | 32,760円 | |
上記に加え、食費・水道光熱費・医療費・おむつ代などがかかります。
施設介護
Bさんの場合(要介護5、重度の認知症、徘徊あり、特別養護老人ホーム入居)
| サービス内容 | 利用回数 | 費用(自己負担1割) |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
1カ月 | 31,672円 |
| 1カ月の介護保険サービス自己負担額合計(目安) | 31,672円 | |
上記に加え、家賃・食費・生活費などで6万~15万円程度が必要です。
介護サービスの利用にどのくらいの費用がかかるか、自己負担がいくらになるかは以下のサイトで確認できます。
離れて暮らす家族を見守るなら「見守りハピネス」がおすすめ
「最近、実家の親のことが少し心配」「毎日連絡を取るほどではないけれど、何かあったときに気づけるようにしたい」と感じることはありませんか? まだ介護が必要な段階ではないけれど、離れて暮らす親の生活がふと気になるという方におすすめなのが、CSPのシニア向け見守りサービス「見守りハピネス」です。
「見守りハピネス」は、日常生活にそっと安心をプラスして、親の自立した生活をさりげなくサポートします。もしものときのための備えとして、緊急通報ボタンが搭載されており、急な体調不良に見舞われたり、転倒などで助けが必要になったりした場合に、ボタン一つでCSPの指令センターにつながる仕組みで、状況に応じて家族への連絡はもちろん、パトロール員が駆けつけて対応します。
親と子供のどちらも安心して生活を送るための選択肢として、ぜひ「見守りハピネス」の利用をご検討ください。
まとめ
要介護5は、日常生活全般にわたって支援を必要とする重度の介護状態です。そのため、適切なサービスの利用や家族のサポートが欠かせません。在宅介護を行うには、住環境の整備や介護体制の構築などが重要で、介護する家族の心身のケアも欠かせません。経済的な負担を軽減するためには、助成金や給付金を有効に利用しましょう。
また施設介護は、専門的なケアを24時間受けられる安心感がある一方、費用や環境変化への配慮が必要です。在宅介護と施設介護のどちらを選択するにしても、本人の意向や状態、家族の状況を総合的に考慮することが大切です。
まだ介護は必要ないけれど、離れて暮らす家族の生活が気になるという方には、CSPのシニア向け見守りサービス「見守りハピネス」がおすすめです。カメラを使わず、緊急通報ボタンや各種センサーで、安全・安心な暮らしをサポートします。ご家庭の安全に関してお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の詳細ページはこちら↓
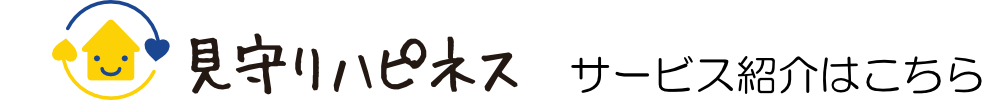
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ+」
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の資料請求やお見積り依頼はこちら↓
おすすめ記事