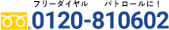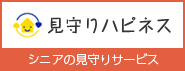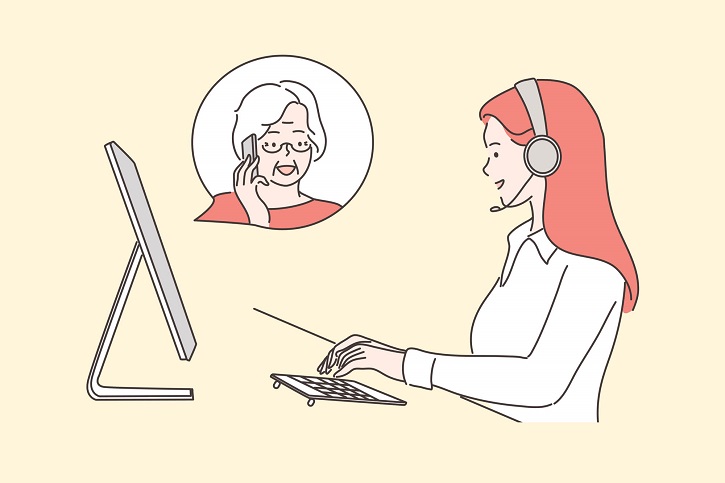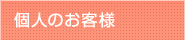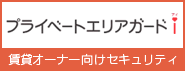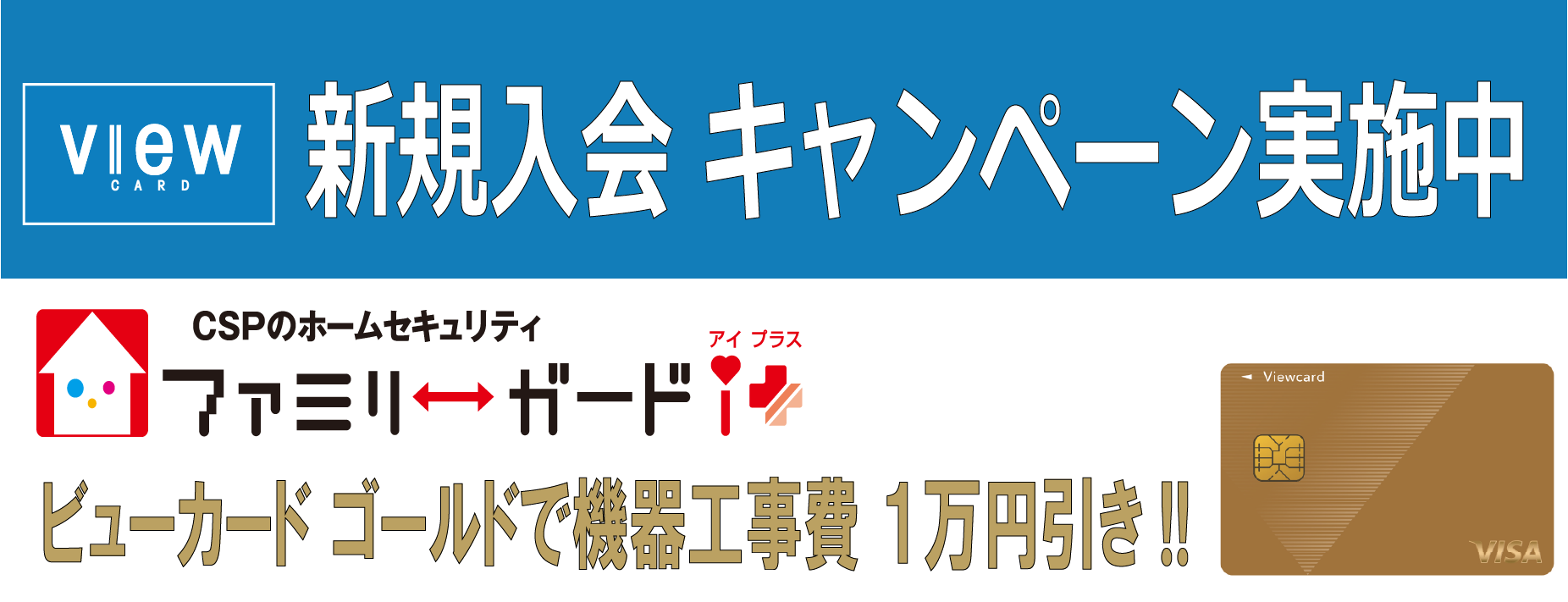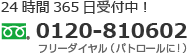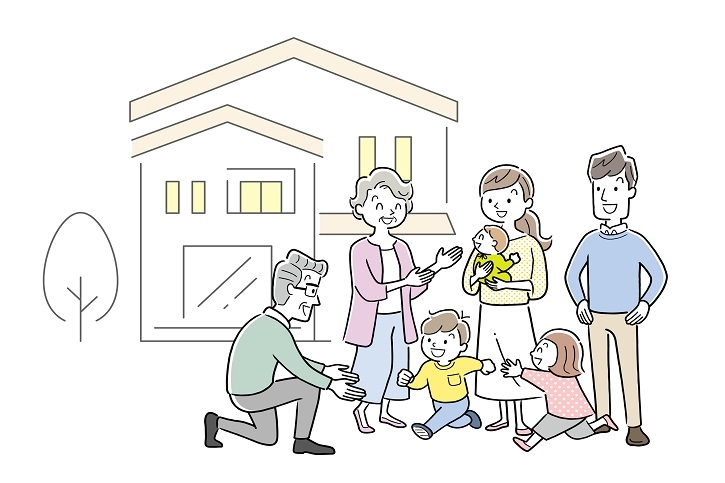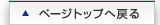CLOSE
- CSP セントラル警備保障 | 警備・防犯・防災・情報セキュリティ >
- 個人のお客様 >
- ホームセキュリティコラム >
- 備えて安心!家庭の防災備蓄品リストと選び方を解説
備えて安心!家庭の防災備蓄品リストと選び方を解説

災害大国といわれる日本では、地震や台風、豪雨などの自然災害が頻繁に発生します。家庭での防災備蓄は、いざというときの暮らしを支える重要な備えです。最低限の飲料水や食料、生活用品を備えておくことで、不安や負担を軽減できます。
この記事では、大切な家族と自分自身を守るために、家庭で準備しておくべき防災備蓄品を詳しくご説明します。必要最低限の必須アイテムから、備えておくことで安心感が増すおすすめグッズまで、具体的なリストと選び方のポイントをお伝えしますので、ぜひこの機会に防災の準備を始めてみましょう。
- なぜ家庭での防災備蓄が重要なのか?
- 水や食料は最低3日分、できれば7日分を準備しよう
- 家庭でそろえるべき防災備蓄品リストと3日分の目安量
- あると便利な防災備蓄品
- 防災備蓄品を準備する際の注意点
- まとめ
なぜ家庭での防災備蓄が重要なのか?
災害から大切な命と暮らしを守るためには、日頃からの備えが非常に重要です。中でも、防災備蓄品は、災害発生直後の混乱期を乗り越えるために欠かせません。
ここでは、防災備蓄の重要性をご説明します。
災害は予測不可能
自然災害は、いつ・どこで発生するか予測できません。「まさか自分が被災することはないだろう」と思っていても、ある日突然、その「まさか」が現実となる可能性があります。警報が出てから準備を始めても、間に合わない可能性があります。
また、災害が発生すると、電気・ガス・水道といったライフラインが寸断され、水や食料、さらに情報も手に入らない状況に陥る可能性を十分に想定しておかなければなりません。このような状況下で、自力で生活を維持するために、事前に備蓄をしておくことが不可欠になります。
公助には限界がある
災害発生直後は、行政や消防、警察などの公的な支援がすぐに届かない場合があります。特に大規模な災害が発生した場合、被災地域全体が混乱し、救助や物資の供給に時間がかかるでしょう。
2011年に発生した東日本大震災の際にも、広範囲にわたる甚大な被害により、多くの地域で公的支援がすぐに届かず、自助の備えがいかに重要であるかが浮き彫りになりました。そのため、まずは自分の身と家族の安全を確保するために、行政による公助だけに頼るのではなく、自助の備えを用意しておくことが不可欠なのです。
家庭を守るための備え
住み慣れた家は最も安心できる場所ですが、災害が発生すれば、その安全が脅かされる可能性があります。しかし、必ずしも避難所へ移動することが、最善の選択肢とは限りません。
避難所の開設の遅れや収容人数の制限、衛生面やプライバシーの問題など、避難所生活にはさまざまな課題があることも事実です。防災備蓄は、避難生活を送る上での備えであると同時に、自宅で安全に過ごすための備えでもあります。
水や食料の備蓄に加え、電気やガスが使えなくても調理できるカセットコンロや、断水時にも役立つ簡易トイレなどがあれば、自宅での生活を続けやすくなります。
水や食料は最低3日分、できれば7日分を準備しよう
ライフラインが寸断され、物流が滞る可能性のある災害発生直後を乗り切るためには、最低限の備えが不可欠となります。ここでは、具体的にどのようなものを備えておけばいいのか詳しくご説明します。
最低でも3日分、できれば7日分が必要
災害が発生し、電気・ガス・水道などのライフラインが停止すると、普段どおりの生活は困難になります。特に、食料や水の確保は生命維持に直結するため、非常に重要です。
自宅での避難生活を想定して、最低でも3日分、できれば1週間分の備蓄が必要だといわれています。これは、大規模な災害時には物流が滞り、すぐに物資が届かない可能性があるからです。
水や食料品の備蓄は、以下の3段階で行うことをおすすめします。
災害発生当日に調理不要で食べられる1日分の備え
災害発生直後は、混乱しているため火を使うことが難しい場合があります。そのため、開封してすぐに食べられるものや、温めなくてもおいしく食べられるものを用意しておくと安心です。
国などからの食料が届くまでの3日分の備え
災害発生から3日程度は、公的支援がなかなか届かないことが想定されます。この期間を自力で乗り切るための備蓄が必要です。
食料の供給が滞る場合の1週間分程度の備え
大規模な災害や広範囲にわたる被害の場合、食料の供給が完全に安定するまでに、1週間以上かかることもあります。より安心して生活を送るために、7日分の備蓄を目指しましょう。
食料品の例
具体的にどのような食料品を備蓄すればいいのか、食料品の例をご紹介します。
水
飲料水だけでなく、生活用水としても必要になるため、1人1日3リットルを目安に、最低でも3日分、できれば7日分を備蓄しましょう。
調理せずに食べられる食料品
即席麺やカップ麺、レトルトご飯やアルファ米、レトルト食品などは、お湯やお水があれば手軽に食べられます。また、パンやお菓子、肉・魚・豆などの缶詰は、そのまま食べられるので便利です。
粉ミルク・離乳食
乳幼児がいる場合は、月齢に応じたミルクやベビーフードも必須です。ほ乳瓶やスプーンの消毒が難しい場合を考え、衛生的に使用できるものを選びましょう。
介護食
高齢者や飲み込むことが困難な方がいる場合は、レトルトの介護食や栄養補助食品の備蓄も必要です。
食料品以外の必須アイテム
食料品と合わせて準備しておきたい、災害時に役立つアイテムをご紹介します。
ラジオ
災害発生時の情報収集に欠かせません。手回し充電式や電池式がおすすめです。
懐中電灯
夜間や災害時の災害発生に備えて、各部屋に1つずつ置いておくことをおすすめします。
電池
ラジオや懐中電灯、モバイルバッテリーなどに使用するため、種類も本数も多めめに備蓄しておきましょう。
モバイルバッテリー
スマートフォンなどの充電に必要です。災害時は情報収集や連絡手段として、スマートフォンが非常に重要になります。
簡易トイレ
断水などで水洗トイレが使えなくなることも考えられるため、排泄物を処理するための簡易トイレは必須です。凝固剤と処理袋がセットになったものが便利です。
トイレットペーパー
普段から多めにストックしておけば、万が一のときも困りません。
常備薬
家族が日常的に服用している薬は、数日分~1週間分程度を備蓄しておきましょう。お薬手帳のコピーや主治医の連絡先なども、一緒に保管しておくと安心です。
家庭でそろえるべき防災備蓄品リストと3日分の目安量
災害発生から3日間を乗りきるためには、どれぐらいの量が必要なのでしょうか? ここでは、家庭でそろえるべき防災備蓄品の具体的なリストと目安量を詳しくご説明します。
食料品の目安
水 9L
1人あたり1日3Lを目安に、3日分で9Lは確保しましょう。飲料水だけでなく、体を拭いたり、食器を洗ったりする生活用水としても使用します。
即席麺やカップ麺 1個
お湯があれば手軽に食べられるので便利です。3日分で1個用意しましょう。
パン 1食
1食分として、賞味期限の長いロングライフパンなどを備蓄しておくとよいでしょう。
レトルトご飯・アルファ米 7パック
水やお湯で調理できるため、非常食として優秀です。7パック程度あれば、主食として十分活用できます。
レトルト食品 2パック
カレーや丼ものの具など、温めなくても食べられるものを選ぶと便利です。2パック程度備蓄しておきましょう。
肉・魚・豆などの缶詰 5缶
タンパク質源として重要です。ツナ缶やサバ缶、焼き鳥缶、豆の水煮缶など、5缶程度は用意しておきましょう。栄養バランスを考慮して、さまざまな種類をそろえるのがおすすめです。
乾物(かつお節・桜エビ・煮干しなど) 適量
味噌汁やご飯に混ぜるなど、少量でも風味や栄養をプラスできます。
豆腐(充てん) 1食
充てん豆腐はタンパク質が豊富で、常温保存できるため、非常食として役立ちます。1食分は用意しておくとよいでしょう。
粉ミルク・離乳食 9食
乳幼児がいる場合は必須です。1日3食として3日分で9食は必ず用意してください。
介護食 9食
高齢者や飲み込むことが困難な方がいる場合は、レトルトの介護食を1日3食として3日分で9食備蓄しておきましょう。
お菓子 3食
エネルギーの補充だけではなく、ストレス軽減や気分転換にもなります。チョコレートやビスケットなど、高カロリーで日持ちするものや、個包装のものがおすすめです。3食分程度用意しておくとよいでしょう。
生活用品
衣類 3組
着替えとして、季節に合わせたものを3組程度は用意しておきましょう。
下着 3組
衣類と同じく3組程度は必要です。
靴 1足
避難時や災害復旧作業時に安全に活動できるように、歩きやすい丈夫な靴を1足用意しておきましょう。
レインコート 1着
雨天時の移動や作業に役立ちます。1着は必要です。
軍手 1双
ガラスの破片や瓦礫から手を保護する際に役立ちます。1双は用意しておきましょう。
毛布 1枚
夜間の冷え込みや、体を休める際に使用します。非常用ブランケットもコンパクトで便利です。
ラジオ 1台
災害情報や安否情報など、正確な情報を得るために欠かせないため、一家に1台は必要です。
懐中電灯 1灯
できれば家族の人数分をそろえたいですが、最低でも1灯は準備しておきましょう。
電池 各種1箱
使用する機器に合わせて各種1箱ずつ必要です。
モバイルバッテリー 1個
大容量のものやソーラー充電タイプを準備し、常に充電しておきましょう。
使い捨てカイロ 3個
冬場の防寒対策に役立ちます。1日1個を目安に3個程度は備蓄しておきましょう。
ビニール袋 1パック
ゴミ袋としてはもちろん、雨よけや防寒対策、簡易トイレの処理など、幅広い用途で活用できます。大小さまざまなサイズのものを1パック用意しておくと便利です。
衛生用品
トイレットペーパー 3ロール
1日1ロールを目安に、3ロール程度は備蓄しておきましょう。
ティッシュペーパー 1箱
1箱は必要です。
歯ブラシ 1本
口腔ケアは感染症予防にもつながります。1人1本は用意しましょう。
簡易トイレ 15回分
1日5回分として3日分で15回分は用意してください。
マスク 3枚
粉塵や埃の吸入防止や感染予防に、1日1枚を目安に3枚程度は備蓄しておきましょう。
救急用品 1セット
絆創膏や消毒液、ガーゼ、包帯、体温計など、基本的な救急用品を1セットにまとめておきます。
タオル 3枚
1日1枚を目安に、3枚程度は備蓄しておきましょう。
生理用品 15枚
女性にとっては欠かせないものです。15枚程度は用意しておきましょう。多めに備蓄しておくと安心です。
おむつ 15枚
1日5枚として3日分で15枚は必ず用意してください。
貴重品
現金 2万円
停電時にはATMが使えず、スマートフォンやクレジットカードも利用できない可能性があります。1000円札と100円玉、10円玉を中心に、2万円ほどの現金を用意しておきましょう。公衆電話や自動販売機の利用にも小銭が役立ちます。
あると便利な防災備蓄品
食料や水、最低限の生活必需品をそろえることはもちろん大切ですが、災害時の不便な生活を少しでも快適に、そして安全に乗り切るためには、さまざまなアイテムが役立ちます。
ここでは、ぜひ準備しておきたい、あると便利なアイテムをご紹介します。
カセットコンロ
停電やガスが止まった際に、温かい食事を作るために非常に役立ちます。カセットボンベも多めに備蓄しておきましょう。
ウェットティッシュやウエットタオル
手指の消毒やちょっとした汚れを拭き取る際に活躍します。また、断水時にお風呂に入れない状況でも、体を拭いて清潔に保てます。
ラップ
食器に敷いて使用すれば、洗い物を減らすことができ、水の節約になります。
新聞紙
防寒対策として衣類の中に挟んだり、食器を拭いたりと、さまざまな使い道があります。
ランタン
懐中電灯と異なり、広範囲を照らすことができるため、停電時の生活空間を明るく保てます。
ポリタンク
断水時に給水車から水を受け取ったり、生活用水を確保したりするために欠かせません。
割り箸・紙皿・紙コップ
洗い物ができない状況で重宝します。
防災備蓄品を準備する際の注意点
防災備蓄品の準備を進める際には、いくつかの注意点があります。ここでは、備蓄品をそろえる際に知っておくべきポイントを解説します。
家族構成に合わせて用意する
備蓄品は、家族の人数分だけでなく、年齢や性別、健康状態などを考慮して用意することが重要です。乳幼児がいる家庭では粉ミルクやおむつ、アレルギーを持つ家族がいる場合はアレルギー対応食品など、それぞれのニーズに合わせた品目を備えましょう。
防災備蓄品のリストを作成する
準備すべき品目や量を把握するためにも、リストを作成することをおすすめします。リストがあれば、買い忘れを防ぎ、過不足なく備蓄品をそろえることができます。
リストは家族で共有し、定期的に見直しましょう。
素早く持ち出せる場所に保管する
非常時に持ち出す「非常用持ち出し袋」は、玄関や寝室など、すぐに手に取れる場所に保管しましょう。自宅で避難生活を送るための備蓄品は、比較的取り出しやすい場所にまとめて保管することをおすすめします。
定期的に防災備蓄品を点検・交換する
備蓄品には賞味期限や使用期限があるものがほとんどです。年に一度は点検日を決め、期限切れになっていないか確認し、期限が近づいているものは消費して新しいものと入れ替える「ローリングストック法」を取り入れましょう。
まとめ
災害はいつ起こるか分かりません。そのため、日頃から適切な防災備蓄品を備えておくことは、災害発生時における二次的な被害を軽減し、避難生活の困難さを和らげ、大切な家族の安全を確保するために非常に重要です。
また、日々の暮らしをより安全・安心なものにするために、ホームセキュリティという選択肢もあります。防災への備えと併せて、留守中の住まいの見守りなど、さらなる安全・安心のために、CSPの「ファミリーガードアイ+」の導入をぜひご検討ください。
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ+」の詳細ページはこちら↓
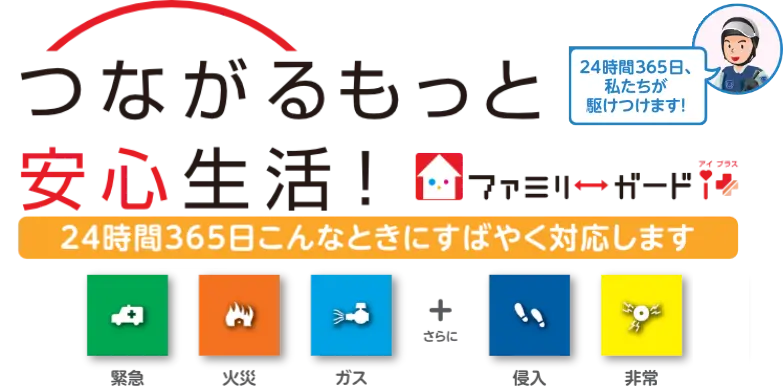
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ+」
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の資料請求やお見積り依頼はこちら↓
おすすめ記事