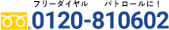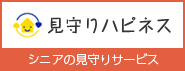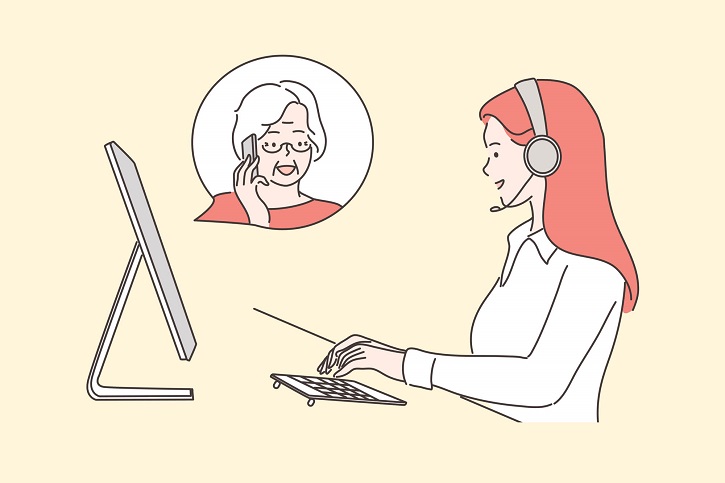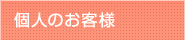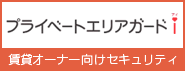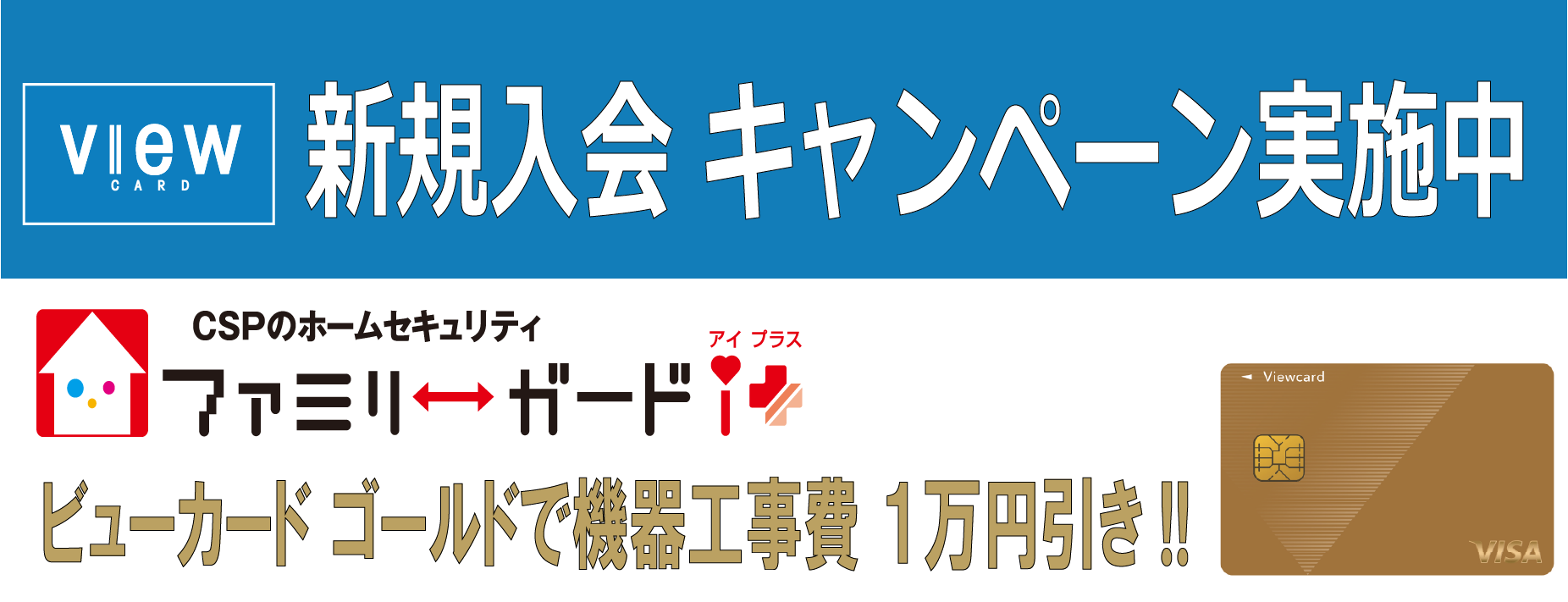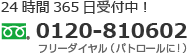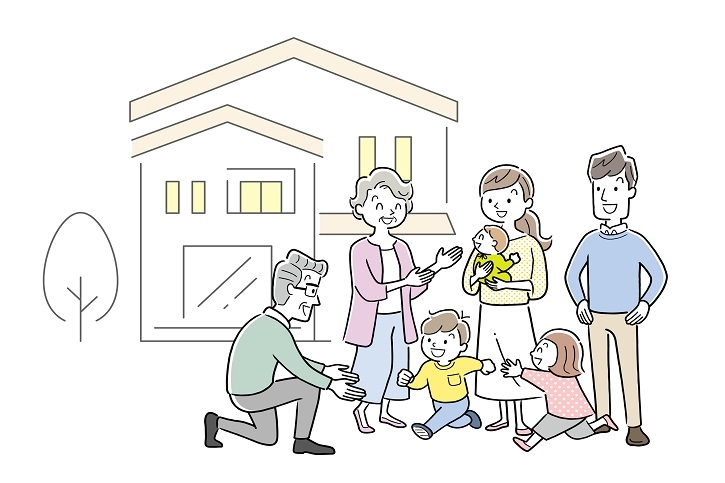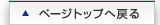CLOSE
- CSP セントラル警備保障 | 警備・防犯・防災・情報セキュリティ >
- 個人のお客様 >
- ホームセキュリティコラム >
- 遠距離介護とは?必要な準備と成功させるポイントを徹底解
遠距離介護とは?必要な準備と成功させるポイントを徹底解

高齢になった親の介護が必要になったとき、近くにいることが難しい方も多いでしょう。近年、遠く離れて暮らす親の介護をどうするか悩む家庭が増えており、遠距離介護が注目されています。遠距離介護は、物理的な距離だけでなく、情報収集の複雑さや緊急時の対応への不安など、多くの課題を伴います。
しかし、適切な準備とサポートがあれば、離れた場所からでも親を支え、自分自身の負担を軽減することは可能です。
この記事では、遠距離介護を始めるにあたって知っておくべき基礎知識や、必要な準備と成功させるポイントと併せて、安心できる見守りサービスについて詳しくご説明します。
遠距離介護とは?
親の介護が必要になった際に、離れて暮らしていると、「どのようにサポートすればいいのだろう」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。住み慣れた場所を離れたくない親の気持ちを尊重しつつ、遠距離から介護を続けることは、想像以上に大変なことです。
しかし、近年では仕事や家庭の事情で親の近くに住めない人が増え、遠距離介護が一般化しつつあります。ここでは、遠距離介護とは何か、その現状や選ばれる理由についてご説明します。
遠距離介護とは
遠距離介護とは、主に親と離れて暮らしている子供が、親が自立した生活を送れるように、離れた場所からサポートを行うことです。例えば、都市部で働く子供が、地方に住む親の介護を行う場合などが該当します。
遠距離介護の現状
近年、核家族化や少子高齢化により、親と子供が離れて暮らすケースが増加しています。それに伴い、遠距離介護の必要性も高まっており、厚生労働省の調査からもその現状が明らかになっています。
厚生労働省が2022年(令和4年)に実施した「国民生活基礎調査の概況」によると、同居の配偶者や子供などが介護する割合が45.9%を占めているのに対し、別居の家族等が介護をする割合は11.8%でした。これは、同居している家族による介護が主流であるものの、遠距離から介護を行う家族がある程度存在することを示しています。
現在、親と離れて暮らしていて、将来の介護に不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。しかし、このデータからは、必ずしも介護のために同居が必要ではないということが分かります。
出典:厚生労働省「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」
遠距離介護を選ぶ理由
遠距離介護を選択する理由はさまざまですが、大きく分けて以下の2つが挙げられます。
親が住み慣れた土地での生活を望む
遠距離介護が選ばれる理由の一つが、住み慣れた土地で生活を続けたいという親の希望です。多くの高齢者は、自分の居住地に愛着を持っており、慣れない場所へ移り住むことへの抵抗感や不安は大きく、環境の変化が心身の負担となることも少なくありません。
そのため、親孝行の観点からも、親の意思を尊重したいと考える子供世代が多く、結果として、親が住む遠隔地で介護を継続するという選択に至ります。
介護する側の社会的な立場
介護を行う側の社会的な立場も、遠距離介護が選ばれる理由の一つです。子供世代は自身の家庭を持ち、仕事や子育てなど、多岐にわたる責任を抱えています。
特に、仕事においては、キャリア形成や経済的な安定のために、今の職場や居住地を離れることが難しい場合がほとんどです。また、子育て中の場合も、子供の学校や友人関係など、生活の基盤がすでに確立されているため、安易に引っ越しを選択できないでしょう。
このような背景から、親子の双方ができる限り無理のない形で支え合うための手段として、遠距離介護というスタイルが選ばれています。
遠距離介護のメリット・デメリット
遠距離介護は、親と離れて暮らす家族にとって、現代の社会事情に適応した介護の形態ですが、当然ながら良い面だけではなく課題もあります。ここでは、遠距離介護がもたらすメリットとデメリットをご紹介します。
メリット
転居しなくて済む
遠距離介護の大きなメリットは、介護者が自身の生活基盤を維持できることです。仕事や子育てなど、現在の環境を大きく変える必要はありません。
親にとっても、住み慣れた地域や家で生活を続けられることは、精神的な安定につながります。無理な転居を避けることで、親子の双方の心身の負担を軽減し、安定した生活を送れるでしょう。
精神的・肉体的ストレスが軽減される
同居介護では、24時間体制の介護が大きな精神的・肉体的負担となることがあります。遠距離介護であれば、日常的な身体介護をプロのサービスに任せることで、介護者の負担を大幅に軽減できます。
介護者が自身の時間を確保し、心身の健康を保ちやすくなることで、よりよい介護にもつながるでしょう。
介護保険サービスを利用しやすい
遠距離介護は、家族と同居しているケースと比べて、介護保険サービスを利用しやすいというメリットがあります。
親が一人暮らしの場合や高齢者のみの世帯である場合、生活状況が考慮され、訪問介護による掃除や調理などのサービスを受けやすくなります。さらに、介護施設への入所を検討する際にも、優先的に入居できる可能性があります。
これは、「同居介護の高齢者よりも支援の必要性が高い」と判断されることがあるためです。介護施設、特に特別養護老人ホームへの入所は非常に待機者が多く、数年待ちとなることも珍しくありません。遠距離介護は、介護施設への入所を早める上で、有利に働く場合があります。
デメリット
日頃の様子が把握できない
遠距離介護の大きな課題は、親の日々の様子を細かく把握しにくい点です。体調の急な変化やケガ、気分の落ち込みといった些細な異変に気づきにくいことがあります。
一人暮らしの親の場合、緊急時にすぐに助けを呼べないリスクも考えられます。そのため、異変を早期に察知するための仕組みづくりが非常に重要です。
費用の負担が大きい
遠距離介護は、経済的な負担が増大する傾向があります。親元への定期的な訪問にかかる交通費や宿泊費、介護保険外の家事代行や食事宅配サービスなどの利用料がかさむことがあるからです。
費用が積み重なることで、介護者の家計を圧迫する可能性があるため、経済的な計画をしっかりと立てておくことが重要です。
緊急時の対応が難しい
遠距離介護における最も大きなデメリットともいえるのが、緊急時の対応の難しさです。親が急な体調不良やケガ、災害に見舞われた際も、すぐに駆けつけることはできません。
病院への搬送や手続きなど、迅速な対応が求められる場面でも、物理的な距離が障壁となるでしょう。
遠距離介護を始めるために必要な準備
親の介護が視野に入ってきた際に、「何から手をつければいいのだろう」と戸惑う方も多いでしょう。遠距離介護をスムーズに進めるためには、事前の準備が何よりも大切です。
ここでは、遠距離介護をスタートさせるために必要な準備についてご説明します。
親とコミュニケーションをとる
遠距離介護の最初の一歩は、親とのコミュニケーションです。介護の話はデリケートですが、親の状態を的確に把握し、意向を尊重することが重要です。
日頃からこまめに連絡を取り、現在の体調や日常生活での困りごとについて優しく耳を傾け、信頼関係を築くことから始めましょう。
親の生活パターンと資産状況を把握する
介護計画を立てるには、親の日々の生活実態と経済状況の把握が不可欠です。食事や外出頻度、習い事、趣味など、起床から就寝までの生活パターンを把握することで、どのような支援が必要なのかが見えてきます。
また、親の資産状況を確認しておくことも大切です。介護にかかる費用を計算し、必要に応じて介護保険や資産の利用計画を立てることが、経済的な負担を軽減するポイントとなります。
親の人間関係を把握する
離れて暮らす親の介護では、近隣との連携が重要です。親しい友人や知人、近所の方、主治医など、身近な人々の情報を把握し、いざというときに連絡が取れるように、連絡先を控えておくことが欠かせません。
周囲の人々は、親の日々の様子を把握していることも多く、緊急時に初期対応を手伝ってくれる可能性のある貴重な存在となります。町内会や民生委員など、地域のコミュニティとのつながりも確認し、必要に応じて協力を依頼できる準備を整えておきましょう。
介護の希望を共有する
親の介護に関する具体的な希望を共有することも大切です。「どのような介護を望んでいるのか」「どの施設やサービスに関心があるのか」など、具体的に話し合いましょう。
希望を共有することで、親の意思を尊重した選択ができ、不安の軽減にもつながります。
介護サービスの情報を収集する
親の状況と希望を把握したら、次に必要なのが、利用できる介護サービスに関する情報収集です。まずは、親の住む地域の地域包括支援センターに相談することから始めましょう。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口であり、介護保険サービスの利用案内やケアマネジャーの紹介、地域の医療機関や福祉サービスの情報提供など、幅広い支援を行っています。
他にも、介護保険サービスの概要や利用条件、費用についても情報を集めましょう。親の状況に合ったサービスを見つけることが、遠距離介護を継続していく上で不可欠な準備となります。
遠距離介護をスムーズに進めるポイント
親から離れて支援する遠距離介護は、多くの家族にとって新しい挑戦です。距離があっても安心して介護を進めるためには工夫が欠かせません。ここでは、遠距離介護をスムーズに進めるポイントをご説明します。
親とのコミュニケーションを深める
遠距離介護では、親との密なコミュニケーションが最重要です。定期的な電話やビデオ通話を通じて、親の心身の状態や生活の変化を確認しましょう。
コミュニケーションを深めることによって、親との信頼関係が深まり、親自身も安心感を持って生活できます。
介護の役割分担を決める
介護に関わる家族間での役割分担を明確にすることで、負担を均等に分散させることが可能です。例えば、近くに住む家族が実際の介護を担当し、遠くにいる家族がスケジュール管理や経済的な支援を行うといった、具体的な役割を話し合いで決めましょう。
各自の得意分野や生活状況を考慮しながら分担を行うことで、介護におけるストレスの軽減につながります。
介護費用について話し合う
介護にかかる費用は、家庭の経済状況に直結する重要な課題です。遠距離介護の場合、移動費やサービス利用料がかさむことがあるため、事前に家族全員で話し合い、予算を設定しましょう。
また、親自身の資産や公的な支援をどのように活用するかを明確にしておくことも大切です。経済的な負担を軽減するためには、計画的な対応が求められます。
介護休暇や介護休業制度を利用する
介護と仕事の両立は、遠距離介護において大きな課題となることがあるため、国の制度を積極的に利用することを検討しましょう。例えば、介護休業や介護休暇、介護のための短時間勤務等の制度など、仕事と介護の両立支援制度を利用できます。
これらの制度は、介護者の負担を軽減し、離職せずに介護を続けるための重要な支援となります。勤務先の就業規則を確認し、担当部署に相談するなど、事前に制度の利用方法を把握しておけば、いざというときにスムーズに対応できます。
近所の人やプロに協力してもらう
遠距離介護では、介護者の目が届かない部分を補う存在が不可欠です。そのため、親の近隣住民や介護のプロフェッショナルに協力を仰ぐことが非常に重要です。
親しい友人や近所の方に、日頃の見守りをお願いしておきましょう。定期的に様子を見てもらい、異変があれば連絡してもらうことで安心感が増します。
また、介護の専門家であるケアマネジャーと連携することで、地域の介護サービスの情報提供やケアプランの作成、緊急時の対応など、幅広く相談に乗ってもらえます。必要に応じて、訪問介護のヘルパーや訪問看護師といった専門職の力を借りることで、質の高い介護を提供し、親の安全を守りつつ、介護者の精神的な負担も大きく軽減できるでしょう。
公・民のサービスや制度を利用する
遠距離介護では、公的なサービスや自治体の制度を最大限に活用することが重要です。例えば、自治体の安否確認サービスや、介護保険を通じた訪問介護やデイサービスなどは、親の生活を支える上で大きな助けとなります。
また、配食サービスなどを活用した民間の見守りサービスを利用することで、親の安全を守りながら、介護者の負担を軽減することが可能です。特に、警備会社の見守りサービスでは、高齢者の状況確認や緊急時の対応に重点を置いたサポートが行われており、親の自立した生活を支える心強い選択肢として注目されています。
離れて暮らす親の見守りには「見守りハピネス」がおすすめ
警備会社の見守りサービスは、離れていても親の状況を把握し、緊急時の対応を可能にする強力なツールです。CSPの「見守りハピネス」は、緊急通報サービスや多様なセンサーを通じて、離れて暮らす家族の生活を見守ります。
万が一の際にパトロール員が駆けつけるサービスにより、遠距離の不安を軽減し、より安全・安心な毎日をサポートします。また、無料の健康相談サービスや、有料オプションの火災・ガス漏れの監視サービスも利用可能です。
離れて暮らす親の暮らしに不安を感じている方は、ぜひ一度CSPの「見守りハピネス」をご検討ください。
まとめ
遠距離介護は、親の健康と安全を見守りながら、家族の生活も両立させる方法として注目されています。遠距離介護の成功の鍵は、入念な事前準備と各種サービスの活用です。親の生活や希望を尊重しながら、介護制度や民間のサービスなど、便利なサービスを取り入れることが重要です。
遠距離で暮らすからこその「もしも」の不安を解消するなら、CSPの「見守りハピネス」が力になります。「見守りハピネス」は、親の日常をさりげなく見守り、万が一の事態に対応するサービスです。離れていても安心できる環境を提供するために、ぜひ「見守りハピネス」の導入をご検討ください。
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の詳細ページはこちら↓
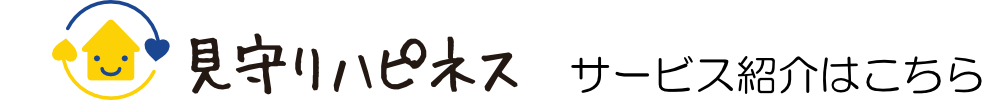
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ+」
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の資料請求やお見積り依頼はこちら↓
おすすめ記事