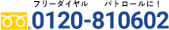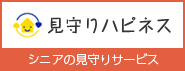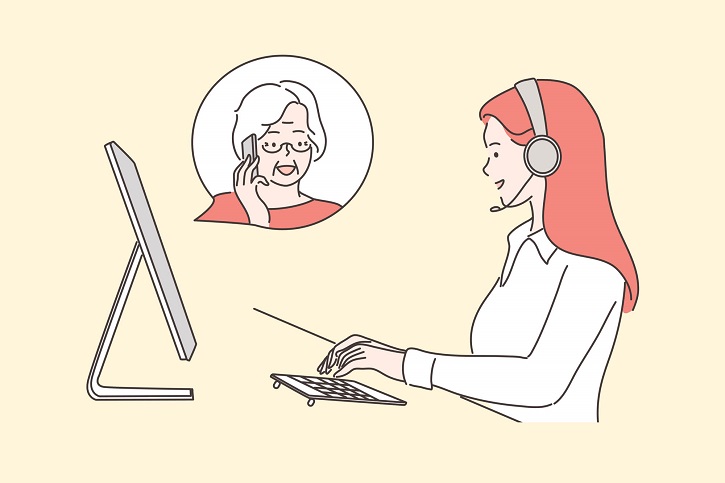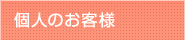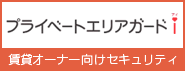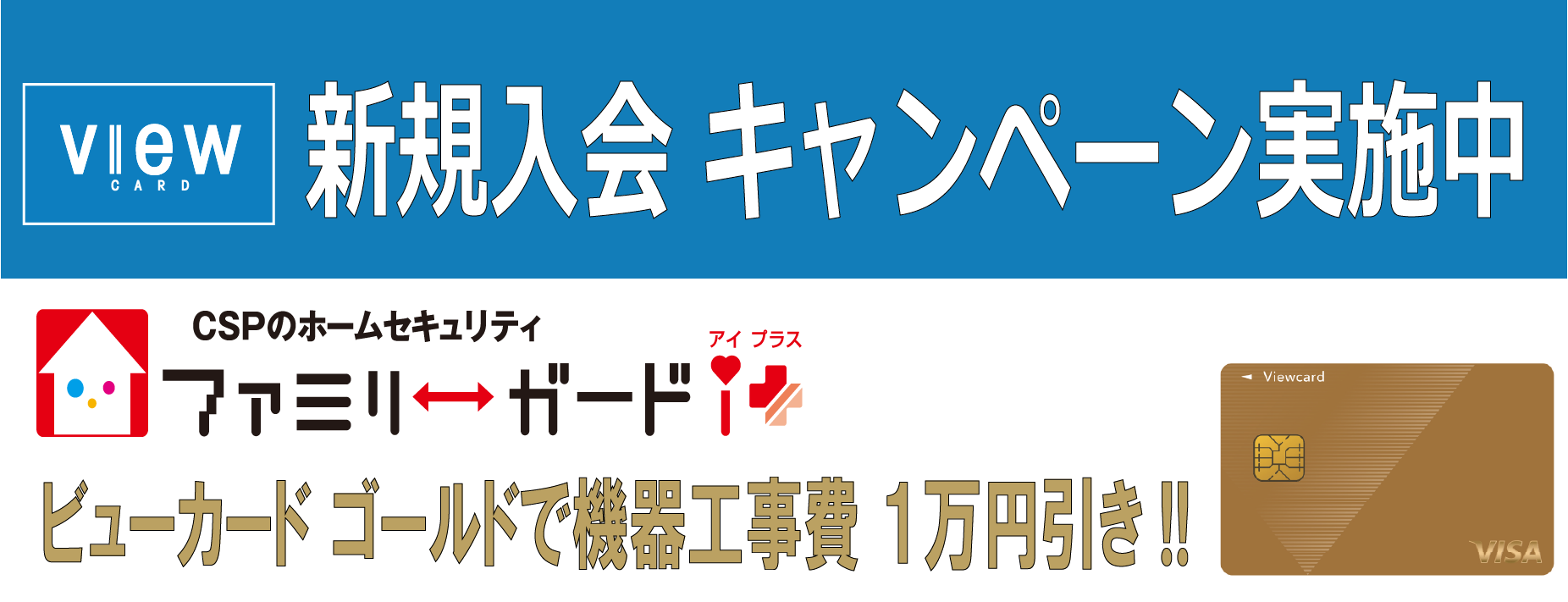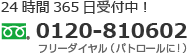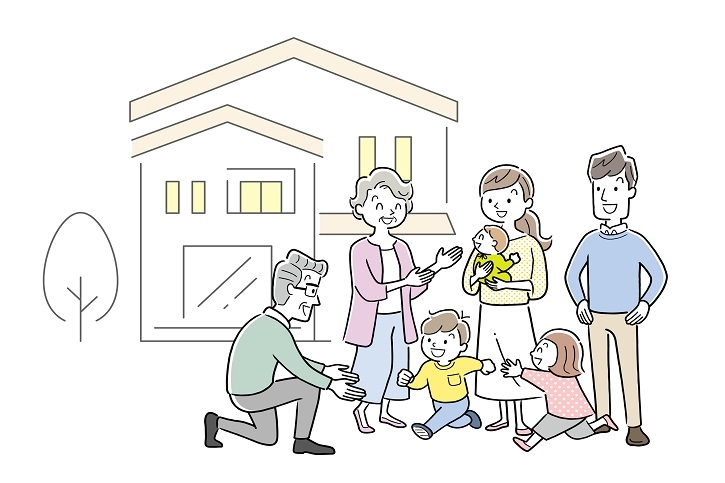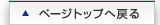CLOSE
- CSP セントラル警備保障 | 警備・防犯・防災・情報セキュリティ >
- 個人のお客様 >
- ホームセキュリティコラム >
- 遠隔でつながる安心感!高齢者見守りサービスの種類と選び方を徹底解説
遠隔でつながる安心感!高齢者見守りサービスの種類と選び方を徹底解説

高齢の親と離れて暮らしていると、「元気に過ごしているだろうか」「何かあったらどうしよう」と心配になるでしょう。そのような不安の軽減に役立つのが、遠隔で利用できる見守りサービスです。最近では、センサーやカメラ、緊急通報システムなど、さまざまな機能を備えたサービスが登場していますが、種類が多く「どれを選んだらいいのか分からない」という方も少なくありません。
ここでは、遠隔で利用できる見守りサービスの種類や特徴、選び方のポイントについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
- 遠隔で利用できる見守りサービスとは?
- 遠隔で利用できる見守りサービスの種類と特徴
- 遠隔でできる見守りサービスを選ぶときのポイント
- 見守りサービス導入前に家族で話し合うべきこと
- ホームセキュリティの見守りサービスなら万が一のときも安心
- まとめ
遠隔で利用できる見守りサービスとは?
遠隔で利用できる見守りサービスがどのようなものか、なぜ必要なのかご説明します。
遠隔で利用できる見守りサービスとは?
近年、スマートフォンやインターネットの普及により、自宅にいなくても高齢の家族の様子を確認できる、「遠隔見守りサービス」が注目を集めています。遠隔見守りサービスとは、センサーやカメラ、スマートデバイスなどを活用して、高齢者の生活を見守るシステムです。
例えば、センサーやカメラを活用することで、異常を検知したらすぐに気づけます。離れた場所からも見守れることで、高齢者が住み慣れた環境で安心して暮らせるでしょう。
遠隔見守りサービスを利用すれば、離れて暮らす家族は安心感が得られ、高齢者は過度に干渉されることなく、日常生活を送れます。
高齢化社会の現状と見守りの重要性
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、65歳以上の高齢者が総人口の約30%を占める時代に突入しました。この割合は今後も増え続けると予想されており、高齢者の単身世帯や高齢者夫婦のみの世帯も増加の一途をたどっています。
そのため、転倒や体調の急変など、日常生活の中で生じるリスクに備える必要性が高まっています。
核家族化による遠隔での見守りのニーズ増加
近年、核家族化が進み、子世代と親世代と離れて暮らすケースが増えています。子世代と親世代の間に物理的な距離があると、日常的に高齢の家族の様子を見に行くことが難しいため、遠隔での見守りに対するニーズが高まっているのです。
また、共働き世帯の増加も、直接的な見守りを困難にする要因の一つです。仕事で忙しい子供世帯にとって、24時間体制で親を見守ることは、身体的にも精神的にも大きな負担となるでしょう。
このような背景から、技術的な手段を活用した遠隔見守りサービスが、効果的な解決策として注目されています。
技術の進化と見守りサービスの多様化
IT技術やセンサー技術の発展により、見守りサービスはますます高度化・多様化しています。センサーやカメラ、スマートデバイス、ウェアラブルデバイスなど、高度な技術を用いた機能が登場しています。
これらの機能を活用することで、離れた場所にいる高齢者の状況をリアルタイムに把握したり、異常の兆候を発見したりすることが可能になりました。また、AI(人工知能)を活用した見守りシステムも開発されており、よりきめ細やかで個別化されたサポートが期待されています。
技術の革新により、高齢者と家族にとって、より安心かつ使いやすい見守り環境が実現しつつあります。
遠隔で利用できる見守りサービスの種類と特徴
遠隔見守りサービスと一口にいっても、さまざまな種類があります。遠隔で利用できる代表的な見守りサービスの種類と特徴をご紹介します。
センサー型
センサー型は、自宅に設置された各種センサーが、高齢者の動きなどを検知し、異常がある場合には通知する仕組みです。例えば、玄関や窓の開閉を検知する「開閉センサー」、室内での人の動きを検知する「人感センサー」、生活反応の有無を検知する「ライフリズムセンサー」などがあります。
カメラ型
カメラ型は、高齢者のリアルタイムの状況を、映像で確認できるサービスです。目視で状況を把握できるため、万が一の際にも適切な対応をしやすくなります。
ただし、プライバシーへの配慮が必要となるため、本人の同意を得た上で導入することが求められます。設置する場合は、プライバシーが守られるように、カメラの設置場所や運用方法を慎重に決めてから導入しましょう。
カメラ型の中には、必要に応じて音声通話が可能な機能を備えたものもあり、離れていてもコミュニケーションを取る手段として活用できます。
IoT型
見守りサービスにも活用されているのが、IoT技術です。「IoT(Internet of Things)」とは、「モノのインターネット」を意味します。簡単にいうと、家電やセンサーなどの「モノ」がインターネットにつながり、情報をやり取りする仕組みです。
例えば、湯沸かしポットや冷蔵庫、テレビなど、日常的に使用される家電にセンサーを内蔵し、その使用状況から生活のリズムを把握する方法があります。「電球が点灯しない」「ポットが使われない」といった小さな異変に、遠隔で気づけることが特徴です。
他にも、スマートスピーカーと連携させたり、見守り機能付き電話やGPSを活用したりすることで、幅広い見守りができるようになります。
スマートフォンアプリ型
スマートフォンの普及により、アプリを活用した見守りも一般的になりました。特別な機器を設置する必要がなく、スマートフォンにアプリをインストールするだけで始められる手軽さが魅力です。
アプリによってできる内容は異なりますが、位置情報や内蔵カメラの動体検知機能で状況を確認したり、緊急時にメッセージを送信したりできる仕組みが取り入れられています。
訪問型
訪問型の見守りは、自治体や民間業者が定期的に高齢者宅を訪問し、安否確認を行う仕組みです。自治体が実施する高齢者見守り活動の他、郵便局員や宅配業者、配食サービスのスタッフが定期的に自宅を訪問し、対面で高齢者の安否を確認するサービスもあります。
訪問型の見守りは、本人の様子や生活環境の変化にも気づきやすく、会話ができるので温かみのある見守りが可能です。直接的な接触を通じて、高齢者の安心感を高めるだけでなく、孤独感の軽減にも役立ちます。
遠隔でできる見守りサービスを選ぶときのポイント
遠隔で利用できる見守りサービスには多くの種類があるため、どのサービスを選ぶべきか迷うこともあるでしょう。見守りサービスを選ぶ際に考慮すべき5つのポイントをご説明します。
親の意向を尊重する
見守りサービスを検討する際には、高齢の親の気持ちを尊重しなければなりません。見守る家族としては、「安心のためにすぐにでも導入したい」と思うかもしれませんが、最も大切なのは見守られる本人の「気持ち」です。
本人が納得し、安心して利用できるサービスを選ぶことが、見守りの第一歩となります。
目的や状況に合わせて選ぶ
見守りサービスを導入する目的は、家庭によってさまざまです。そのため、見守りサービスを検討する際には、「様子を確認したい」「緊急時の対応をスムーズにしたい」など、具体的な目的を明確にすることが重要です。
例えば、日常的な生活リズムを把握したい場合は、センサー型やIoT型が適しています。一方、緊急時の対応を重視する場合は、緊急通報ボタン付きのサービスや駆けつけ型のサービスが有効です。
家族の状況や気になる点に合わせて、必要な機能を持つサービスを選ぶことが大切です。
使いやすさで選ぶ
導入する機器やアプリが複雑であれば、継続的に使うことが難しくなります。高齢者が操作するため、ボタン一つで緊急通報ができるシンプルな仕様や、自動的に情報を送信する機器などをおすすめします。
見守りサービスを長く安心して使うためには、誰にとっても操作が分かりやすいことが重要です。
プライバシーに配慮する
見守りが監視に感じられてしまっては、本来の目的から外れてしまいます。プライバシーへの配慮は、サービスを導入する上で欠かせないポイントです。
例えばカメラ型の見守りは、リアルタイムで状況を確認できるメリットがある一方、常に見られていることに対してストレスを感じる方も少なくありません。カメラ型のサービスに抵抗を感じる場合は、センサー型や訪問型など、プライバシーに配慮した見守りサービスの利用を検討しましょう。
予算に合わせて選ぶ
見守りサービスの導入には、初期費用や月額利用料が必要になることが多いため、無理のない予算の中で選ぶことが大切です。機器の購入費や通信費、サービスの維持費用などを含めて、長期的な視点で比較検討しましょう。
見守りサービス導入前に家族で話し合うべきこと
見守りサービスの導入は、家族の生活に変化をもたらす可能性があります。導入後に後悔しないためにも、事前にしっかりと話し合い、それぞれの思いや気になる点を共有しておくことが大切です。
利用の目的と本人の状況を整理しておく
まず、「なぜ見守りが必要なのか」という目的を整理しましょう。「最近物忘れが増えてきた」「体調の変化が気になる」など、家族が感じている不安を明確にすることで、必要な見守りのタイプや機能が見えてきます。
また、本人の身体的・精神的な状態や生活習慣の把握も欠かせません。具体的な状況を共有することで、より適切なサービスを選べます。
導入する目的を共有しておく
家族間でサービスを導入する目的を共有し、本人にもその意図を丁寧に伝えることが大切です。例えば、「体調の急変に気づけるようにする」「万が一の転倒に備えて」など、具体的で前向きな理由を示すことで、本人の不安を和らげられるでしょう。
「見守り=監視」と感じさせないよう、言葉選びや話し方にも配慮が必要です。
見守りサービスの利用に納得してもらう
高齢者の中には、見守りサービスの導入に抵抗がある方も少なからずいるでしょう。無理に導入してしまうと、本人がストレスを感じてしまうおそれがあるため、納得できる形でサービスを導入しなければなりません。
例えば、「監視されているようで嫌」と感じる方には、映像が記録されないセンサーや家電を選びましょう。機器の操作が苦手な方には、本人の操作が不要のものを選びましょう。他にも、まだ必要ないと感じている方には、高齢を理由にせず、防犯目的のホームセキュリティを選ぶなどの工夫が必要です。
ホームセキュリティの見守りサービスなら万が一のときも安心
ホームセキュリティによる見守りサービスは、遠隔で状況を把握できる上に、緊急時に対応してもらえるため、家族にとっても大きな安心材料となるでしょう。
ホームセキュリティをおすすめする人
ホームセキュリティの見守りサービスは、以下のような方におすすめです。
- 高齢の親が一人暮らしをしている
- 日中に家を空けることが多く、見守りが難しい
- 遠方に住んでいて頻繁に会いに行けない
- 体調の急変や転倒など、万が一の事態が不安
ホームセキュリティの選び方
ホームセキュリティを選ぶ際に押さえておきたい3つのポイントをご説明します。
価格
毎月の利用料金や初期費用を含めて、無理のない範囲で続けられるプランを選びましょう。
質の高さ
センサーの性能やサポート体制の充実度など、サービスの質の高さのチェックも欠かせません。実績のある、信頼できる企業を選ぶことが大切です。
対応
緊急時の対応体制や、24時間365日のサポートがあるかどうかを確認しましょう。
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」とは
CSPの「見守りハピネス」は、ホームセキュリティの中でも、高齢者の方の見守りに特化したサービスです。遠隔から高齢者の生活を見守り、センサーや緊急通報システムを通じて異変を検知します。
万が一の際には、パトロール員が駆けつけて対応する体制が整っているため、家族も安心できるでしょう。
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の詳細ページはこちら↓
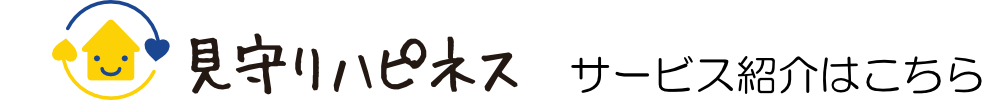
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ+」
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の資料請求やお見積り依頼はこちら↓
おすすめ記事