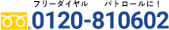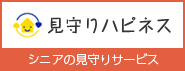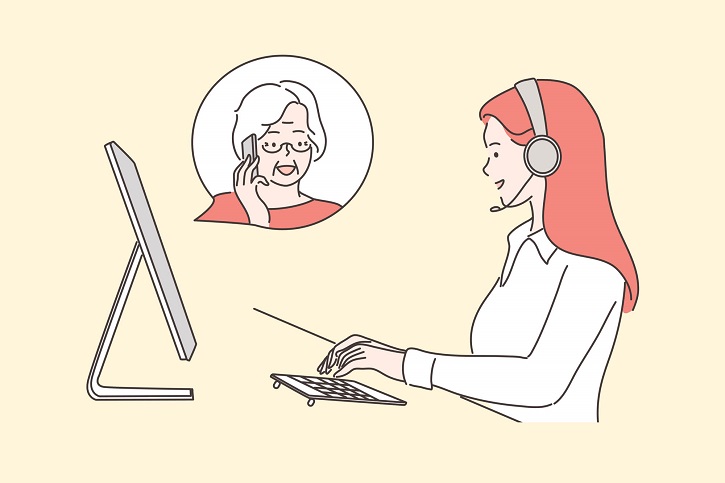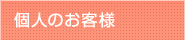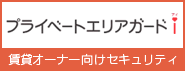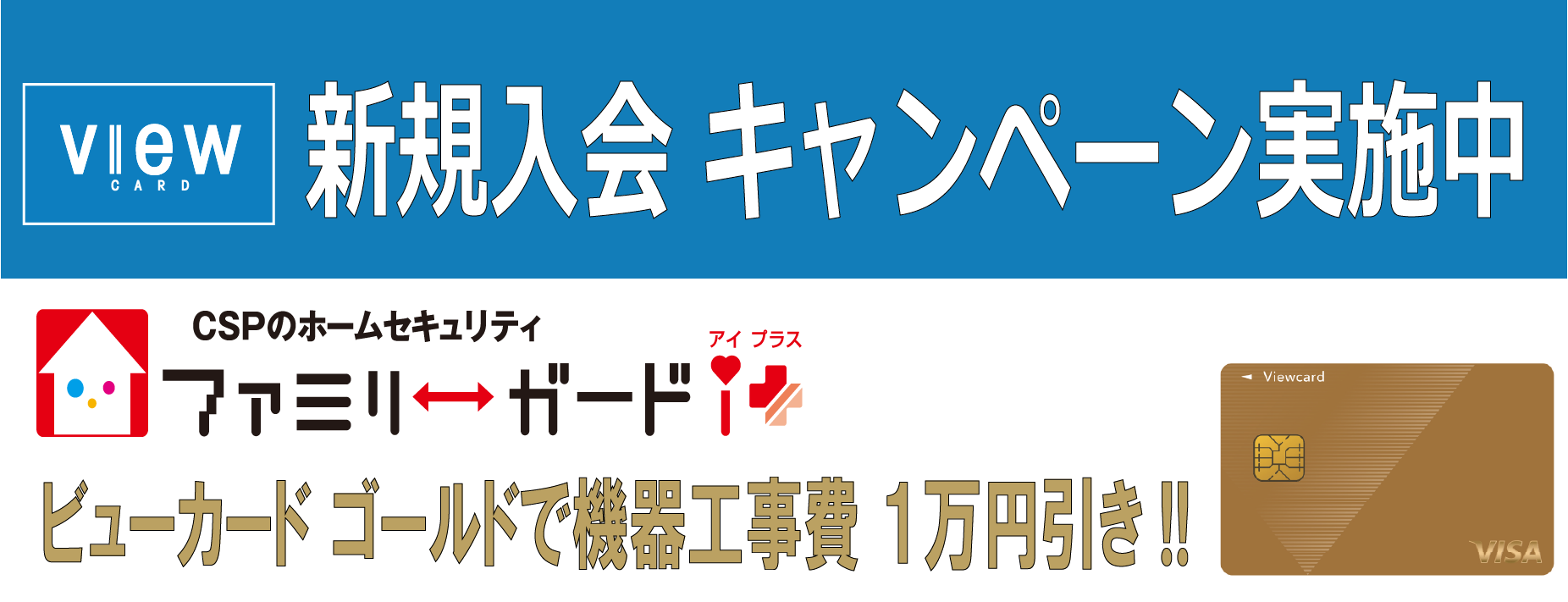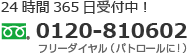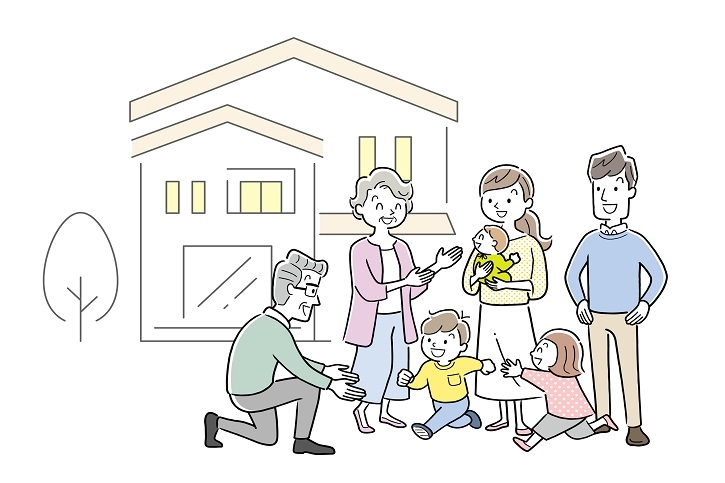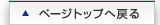CLOSE
- CSP セントラル警備保障 | 警備・防犯・防災・情報セキュリティ >
- 個人のお客様 >
- ホームセキュリティコラム >
- 認知症の見守りに必要なこととは?接し方や注意点、地域の取り組みを解説
認知症の見守りに必要なこととは?接し方や注意点、地域の取り組みを解説

高齢化が進む日本では、認知症と診断される高齢者の数が年々増加しています。大切な家族が認知症になったとき、どのように見守り・支えていけばよいのか、悩む方も少なくありません。認知症になると、わずかな環境の変化にも不安を感じやすく、適切な見守りとサポートが求められます。
ここでは、認知症の基礎知識から、見守りの重要性や具体的なサポート方法まで、詳しくご紹介します。
認知症の基礎知識
近年、ニュースや身近な話題で「認知症」という言葉を耳にする機会が増えています。しかし、実際にはどのような状態を指すのか、明確に理解していない方も多いのではないでしょうか。
認知症とはどのような状態なのか、どのような症状が現れるのか、基本的な知識をご説明します。
認知症とは?
認知症とは、何らかの原因で脳の働きが変化し、記憶力や判断力、理解力といった認知機能が、持続的に低下する状態を指します。年齢を重ねることで誰にでも起こり得るもので、加齢による「物忘れ」とは異なり、日常生活に支障をきたすレベルの変化が現れる点が特徴です。
厚生労働省の推計によると、2040年には日本国内の認知症患者数が約584万人になると見込まれています。家族が認知症になった場合、認知機能の低下に伴い「外出後に家に帰れなくなる」「夜中に徘徊する」といったリスクも高まります。そのため、認知症への理解を深め、早期発見と適切な見守り体制を整えることが重要です。
認知症の主な症状
認知症の症状は多岐にわたり、初期段階では軽微な変化として現れることがほとんどです。特に患者数が多いとされる、4大認知症についてご説明します。
アルツハイマー型認知症
最も一般的なタイプで、記憶障害が主な症状です。物忘れが目立つようになり、徐々に理解力や判断力の低下も見られ、日常の会話や行動に支障が出てきます。
脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血など、脳の血管障害が原因で発症する認知症です。障害を受けた脳の部位によって症状が異なり、血管障害を繰り返すことで段階的に悪化する傾向があります。歩行障害や排尿障害など、身体的な問題も伴うことがあります。
レビー小体型認知症
脳内にできた「レビー小体」というタンパク質が、神経細胞を損傷することで引き起こされます。認知機能の変動や幻視、パーキンソン症状が特徴で、症状が日によって異なるため、診断が難しい場合もあります。
前頭側頭型認知症
前頭葉や側頭葉が萎縮することで起こり、行動や感情のコントロールが難しくなるのが特徴です。比較的若い年齢で発症するケースが多く、言語障害も起こりやすい傾向があります。
認知症の方に必要な「見守り」とは
認知機能の低下に伴い、日常生活を送る上でさまざまな困難が生じることがあります。物忘れや見当識障害、予期せぬ行動などが起こると、本人だけでなく、見守る家族も不安や心配が尽きないでしょう。
認知症の方にとって必要な「見守り」について詳しくご説明します。
認知症の方の見守りとは?
認知症の方の見守りとは、監視や行動の制限を目的とするものではありません。認知症の方は理解力や判断力の低下により、日常生活に危険が伴うことも多いですが、すべてを代行してしまうと、本人の尊厳や生きがいを損なうおそれがあります。そのため見守りでは、本人の自主性や主体性を尊重し、適切な声かけや安全な生活環境を通じて支援します。
認知症は進行性の病気で、現代の医学ではその進行を完全に止められませんが、周囲のサポートによって、本人が安心して生活を送れる環境を整えられます。見守りは、危険を回避しつつ、本人の可能性を引き出しながら支える温かい取り組みです。
認知症の方の見守りで必要なこと
認知症の方の見守りは、ただ様子を見ていればいいというものではありません。適切に見守るためのポイントをご紹介します。
本人の意思を尊重する
見守る上で最も大切なことは、本人の意思や感情を尊重することです。「監視されている」と感じさせてしまうと、本人に過度なストレスを与えかねません。
危険な行為は防ぐ必要がありますが、本人の意向や気持ちに寄り添いながら、安心して過ごせる環境を提供しましょう。
行動の理由を考える
認知症の方の行動には、必ず何かしらの理由があります。例えば、同じことを何度も聞いたり、物を探し回ったりする行動には、不安や混乱、過去の記憶などが影響している可能性があります。
「なぜそのような行動をするのだろう?」という視点を持ち、頭ごなしに制止するのではなく、背景にある感情や欲求を理解しようとすることが大切です。
スキンシップをとる
スキンシップは、認知症の方に安心感を与える重要な手段です。言葉によるコミュニケーションが難しくなっても、触れることでぬくもりは伝わります。
手を握ったり、肩にそっと触れたりするスキンシップは、認知症の方に安心感を与え、情緒の安定につながるでしょう。
生活環境を整える
認知症の方が安全に生活できるよう、生活環境を整えることも重要です。理解力や判断力が低下すると、一人でできないことが多くなり、危険行動につながるおそれがあります。
例えば、段差があるとスムーズに移動できない場合は、手すりやスロープを設置しましょう。また、トイレが不安な場合は、寝室や居間とトイレの動線を短くしたり、寝室にポータブルトイレを置いたりする工夫も必要です。
見守りだけでは、問題が解決しない場合もあるでしょう。状況に応じて生活環境を整える工夫が、解決の手がかりとなることがあります。
認知症の方への地域での取り組み
高齢化が進む日本において、認知症の方は年々増加しています。家族による支援は重要ですが、それだけでは対応が難しいケースも少なくありません。
多くの自治体や地域では、認知症の方とその家族が地域の中で安心して生活を送れるよう、さまざまな取り組みが進められています。自治体や地域が行っている、具体的な取り組みについてご紹介します。
自治体の認知症高齢者等見守りネットワーク事業
多くの自治体では、認知症の方やその家族を地域で支える仕組みとして、認知症高齢者等見守りネットワーク事業が実施されています。これは、地域の住民や関係機関・団体、事業者などが連携し、認知症の方が安全に生活できるように情報を共有し、必要な支援を提供する仕組みです。
例えば、大阪市では、「大阪市認知症高齢者等見守りネットワーク事業」として、事前登録を行った認知症の方が行方不明になった場合、速やかに関係機関と連携して捜索活動を行う体制を整えています。他にも、事前登録を行った認知症の方に、服や靴などに貼付できる見守りシールを渡したり、位置情報探索機器を貸与したりすることで、徘徊などによる事故やトラブルの防止につなげています。
認知症サポーター
認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、認知症の方と家族を可能な範囲で手助けする「認知症サポーター」を育成する全国的な取り組みです。地域住民や地域で働いている人が、認知症に関する基本的な知識や認知症の方への接し方、地域における支援体制などを学ぶ養成講座を受講することで、認知症サポーターになれます。
認知症サポーターは、専門家ではありません。地域の中で、認知症の方や困っている家族を見かけた際に、そっと声をかけたり、さりげない手助けをしたりと、自分のできる範囲でサポートを行います。
例えば、道に迷っている認知症の方に気づいたときに、声をかけて落ち着かせたり、必要であれば地域包括支援センターなどに連絡を取ったりして、認知症の方をサポートします。認知症サポーターが増えることで、地域全体で認知症の方を支える意識が高まり、誰もが安心して暮らせる社会をつくる助けになると期待されています。
見守り・SOSネットワーク
見守り・SOSネットワークとは、認知症の方が行方不明になることを防ぐだけではなく、万が一行方不明になったときも無事に家に戻ることができ、安心して外出を続けられるようにするための自治体の取り組みです。
例えば、目黒区の見守りネットワーク「愛称:見守りめぐねっと」では、下記のように地域における見守りネットワークづくりを推進しています。
地域の団体・機関・商店・企業などの皆さんが、日常の生活や業務の中で、地域のかたの「ちょっと気がかり」なことに気づいた際に、お近くの地域包括支援センターにご連絡いただくことにより、地域をゆるやかに見守っていく取り組みです。
どのような取り組みを行っているかは、自治体によって異なりますので、ぜひ一度住んでいる地域の見守り・SOSネットワークを確認してみましょう。
高齢者の見守りに役立つサービス
高齢者を家庭内だけで見守ることは、家族にとって大きな負担になるでしょう。特に、共働き世帯や遠方に住む家族にとっては、常に様子を確認するのは難しく、見守りが不十分になることもあります。
家族だけで高齢者の見守りを行うのが難しい場合は、専門のサービスを利用することも検討しましょう。高齢者の見守りに役立つサービスをご紹介します。
介護サービスの利用
要介護認定または要支援認定を受けている高齢者なら、介護保険制度に基づくサービスを利用できます。訪問介護やデイサービス、ショートステイ、訪問看護など、さまざまなサービスがあり、専門のスタッフが日常生活のサポートや健康状態の確認を行ってくれます。
また、ケアマネジャーや地域包括支援センターによるサポート体制が整っているため、本人の状態に応じて適切なサービスを計画・提供してもらえるのも大きなメリットです。介護サービスを利用すれば、日々の生活を安全に送れるだけではなく、家族の負担軽減にもつながります。
民間企業の見守りサービスの利用
見守りサービスを行っているのは、自治体だけではありません。近年、民間企業からもさまざまな高齢者見守りサービスが提供されています。
例えば、郵便局員や宅配業者のスタッフ、配食サービスの担当者などが、配達時に高齢者の様子を確認する取り組みが増えています。訪問時の様子を家族に報告したり、異変を感じた場合にはすぐに連絡を取ったりしてくれるので、離れて暮らしていても安心です。
高齢者にとっても、顔なじみのスタッフが定期的に訪問してくれることで安心感が生まれ、孤独感の解消にもつながるでしょう。日常生活に関わる企業が見守りを兼ねることで、より自然な形で高齢者を支えられるようになっています。
ホームセキュリティサービスの導入
最新の技術を活用したホームセキュリティサービスは、防犯対策だけでなく、高齢者の見守りにも役立ちます。センサーによる見守りや緊急通報システム、駆けつけサービスなどにより、24時間365日、高齢者の生活を見守ります。
ホームセキュリティサービスは、高齢者の安心した生活を支え、見守るご家族の精神的な負担軽減にもつながるでしょう。
高齢者の見守りを「見守りハピネス」がサポート
高齢者の見守りは、ご家族だけでは難しい場合があります。特に、一人暮らしの高齢者には、より一層の注意が必要です。
CSPのシニア向け見守りサービス「見守りハピネス」は、長年のホームセキュリティの経験を生かし、高齢者とご家族に安心をご提供します。24時間365日の見守り体制に加え、健康相談サービスやライフリズムサービスなど、きめ細やかなサポートで、高齢者の安全・安心な生活を支援します。
まとめ
高齢者を見守ることは、離れて暮らすご家族にとって大きな安心につながります。健康状態の変化や万が一のトラブルに気づけるだけでなく、高齢者自身の自立した生活もサポートできます。最近では、センサーや通信機能を活用した見守りサービスも充実しており、家族の負担を減らしながら、温かく見守る環境を整えることが可能です。
CSPのシニア見守りサービス「見守りハピネス」は、高齢者の毎日の暮らしを見守るためのサービスです。異常があれば、離れて暮らすご家族にも通知されるため、もしものときも対応が可能です。大切なご家族の安全・安心のために、ぜひ「見守りハピネス」の導入をご検討ください。
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の詳細ページはこちら↓
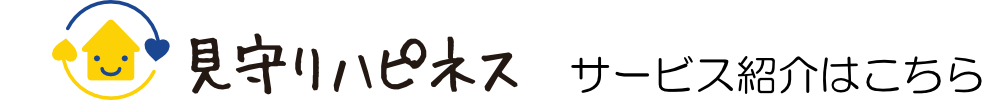
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ+」
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の資料請求やお見積り依頼はこちら↓
おすすめ記事