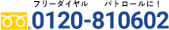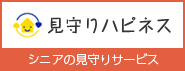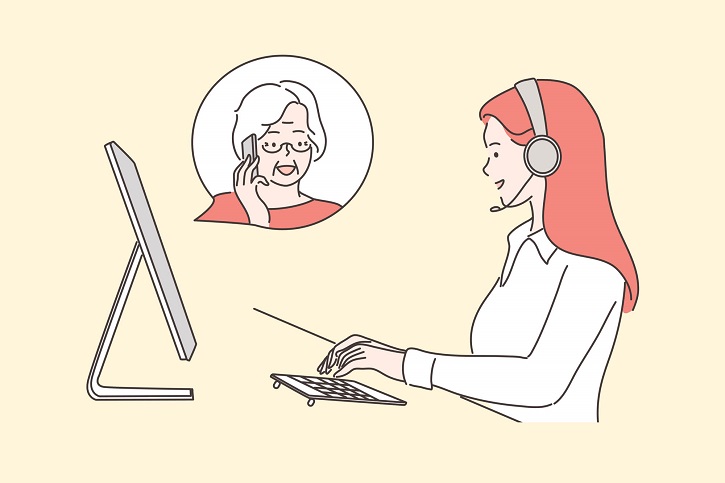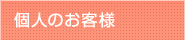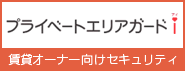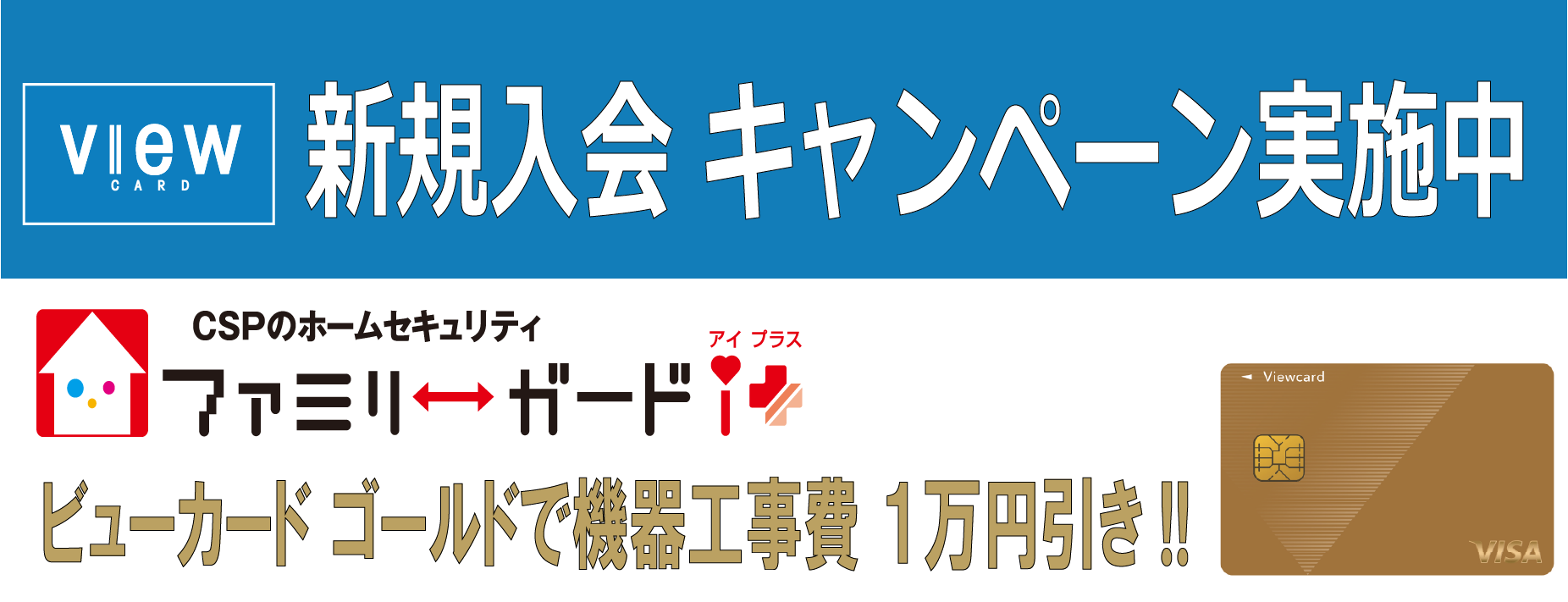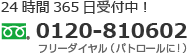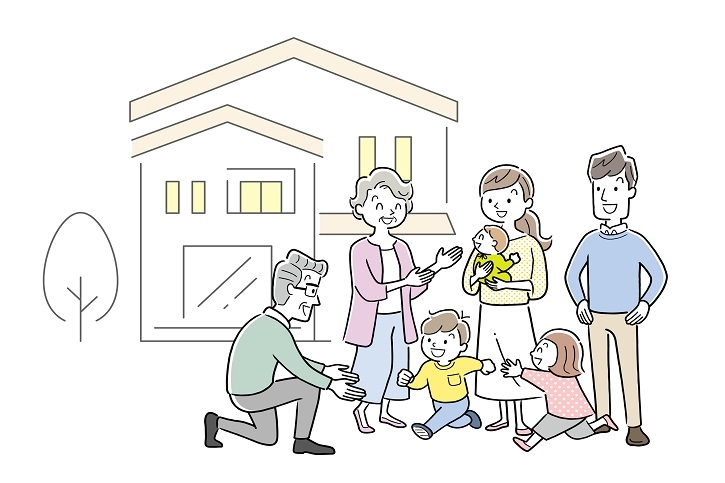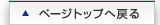CLOSE
- CSP セントラル警備保障 | 警備・防犯・防災・情報セキュリティ >
- 個人のお客様 >
- ホームセキュリティコラム >
- ペットがいてもホームセキュリティは設置できる?注意点や導入方法を解説!
ペットがいてもホームセキュリティは設置できる?注意点や導入方法を解説!

ホームセキュリティに関するお悩みや疑問で多いのが、ペットを飼っていてもホームセキュリティをできるかどうかです。「ペットが動くことでセキュリティシステムが誤作動するのではないか」という不安で、設置に踏みきれない人も少なくありません。
ここでは、ペットを飼っているご家庭にホームセキュリティを設置する際の導入方法や注意点をご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
- ペットを飼っているとホームセキュリティを設置しにくいって本当?
- ペットを飼っているご家庭へのホームセキュリティの導入方法
- ペットを飼っているご家庭がホームセキュリティを設置する際の注意点
- 実はペットには防犯効果がある
- ペットがいてもホームセキュリティは設置できる!
- まとめ
ペットを飼っているとホームセキュリティを設置しにくいって本当?
実際のところ、ペットを飼っているご家庭には、ホームセキュリティを設置しにくい傾向があります。設置しているセキュリティシステムによっては、ペットの動きを検知した際に、空き巣などが侵入したと認識してしまうからです。
ホームセキュリティでは、防犯カメラや火災・ガス漏れセンサー、緊急ボタン、空間(人感)センサーなど、さまざまなセキュリティシステムを設置します。中でも、ペットを飼っているご家庭で生じやすいトラブルが、空間(人感)センサーの誤作動です。
空間(人感)センサーとは、万が一外部から空き巣が侵入した際に、人体が放出する赤外線を検知するセンサーです。空間(人感)センサーはペットと人間を区別できないため、ペットが動き回ることで、センサーが検知してしまう場合があります。
ただし、ペットを飼っているからといって、ホームセキュリティの導入を諦める必要はありません。次の項目では、ペットを飼っているご家庭へのホームセキュリティの導入方法をご説明します。
ペットを飼っているご家庭へのホームセキュリティの導入方法
ペットを飼っているご家庭にホームセキュリティを導入する際には、ペットの動きや安全を考慮した対策が必要です。具体的な導入方法を詳しくご説明します。
空間(人感)センサーの位置や角度を調節する
空間(人感)センサーは、人体が放出する赤外線を検知するセンサーで、万が一外部から空き巣が侵入した際にその体温を検知します。しかし、ペットがいるご家庭では、ペットの動きによって誤作動が発生する可能性があります。
空間(人感)センサーを使用する場合は、センサーの検知角度や距離などの検知エリアを調節することで、ペットの動きによる誤作動を減らせます。例えば大型犬を飼っている場合、大型犬の背丈よりも上の範囲のみ空間(人感)センサーが検知するように調整すれば、誤作動が起こる可能性を下げられます。
また、ペットが通るエリアを事前に把握しておき、空間(人感)センサーの検知範囲とそのエリアがかぶらないように設定することも有効です。
留守中はペットの活動を制限する
空き巣が物色する部屋として多いのがリビングです。リビングで貴重品を保管しているご家庭が多いため、空間(人感)センサーで空き巣を検知するなら、リビングへの設置が効果的です。
ただし、自由に動き回れるペットがいると、リビングに遊びに来た際に空間(人感)センサーが誤作動するリスクが高まるでしょう。したがって、誤作動を防ぐために、留守中はペットの活動を制限することをおすすめします。
例えば、留守中はペットが過ごす部屋を限定し、その部屋には空間(人感)センサーを設置しないという方法があります。また、空間(人感)センサーがあるリビングでペットが過ごす場合は、ペット用のケージや専用のスペースを用意し、留守中はそこにいてもらうことで、センサーの誤作動を防ぐことが可能です。
セルフセキュリティシステムを導入する
警備会社などが提供するホームセキュリティサービスの導入が難しい場合は、セルフセキュリティシステムを導入する方法もあります。セルフセキュリティシステムはその名のとおり、自宅のセキュリティを自分で管理するシステムです。
ペットがいるご家庭では、セルフセキュリティシステムを導入することで、ペットの生活や動きに合わせた柔軟な防犯対策が可能です。例えば、ペット用の見守りカメラを設置すれば、スマートフォンのアプリでカメラの映像をリアルタイムで確認できます。
ペットを飼っているご家庭がホームセキュリティを設置する際の注意点
ペットを飼っているご家庭でもホームセキュリティの設置は可能ですが、導入・使用する際にはいくつかの注意点があります。センサーやセキュリティシステムの誤作動を防ぎ、ホームセキュリティの効果を最大限得るために、注意点も確認しておきましょう。
ペットを飼ったら警備会社に連絡する
ホームセキュリティの導入後にペットを飼うことも少なくありません。ペットを飼い始めたら、まずは警備会社に連絡しましょう。
警備会社にペットの存在を知らせることで、セキュリティシステムの設定や対応をペットに合わせて調整してもらえます。例えば、ペットがいる部屋の空間(人感)センサーの角度を調整するなど、ペットが誤ってセンサーを作動させないように対策を講じてもらえます。
また、警備会社にペットの情報を提供することで、緊急時に適切な対応ができるようになりますので、ペットを飼ったら必ず連絡しましょう。
ペットの種類や大きさで対応が変わる
ペットの種類や大きさによって、セキュリティシステムの対応が異なる場合があります。例えば室内飼いの犬や高い場所を好む猫は、どちらも動きが活発かつ行動範囲が広く、センサーが誤作動する可能性が高いため、センサーを調整する必要があります。
センサーの調整が難しい場合、留守中や就寝時などセキュリティシステムを作動させている間は、ケージや専用の部屋にいてもらうなどの対応が必要です。
一方、鳥やうさぎなど、ケージ内で飼育しており行動範囲が決まっている場合は、センサーの検知範囲内にケージが映らないようにすることで誤作動を防げるでしょう。ペットの種類や大きさに応じた対応を行うことで、セキュリティシステムの効果を最大限に発揮できます。
パトロール員が駆けつけた際の対応
パトロール員が駆けつけた際には、ペットが「逃げない」「噛みつかない」ように工夫しておく必要があります。例えば、玄関に近づかないようにフェンスを置いたり、ケージや専用スペースから出られないようにしたりと、ペットが逃げ出さないように工夫しなければなりません。
また、ペットがパトロール員に対して噛みついたりしないように、ペットの行動を制限することも考慮する必要があります。警備会社に規制のエリアを事前に連絡しておけば、ペットとパトロール員の事故を防げます。
ペットはもちろん、パトロール員の安全を確保するための工夫も必要です。
エアコンを常時使用する部屋での対応
ペットを飼っているご家庭の多くが、エアコンを常時使用しているでしょう。エアコンを常時使用する部屋では、セキュリティシステムの設置に注意が必要です。
エアコンの風や温度変化が空間(人感)センサーに影響を与えるケースがあるため、エアコンの風が直接当たらない位置にセンサーを設置するなど、センサーの位置や角度を調整しなければなりません。それでも誤作動が起こる場合は、空間(人感)センサーの設置を取りやめたり、センサーを別の場所に移動したりする対応が必要です。
セキュリティの質を低下させないように、警備会社に相談しましょう。
実はペットには防犯効果がある
ペットを飼っているとホームセキュリティを設置する際に工夫が必要ですが、実はペットの存在自体に防犯効果があります。特に、「番犬」とも呼ばれていることからわかるように、犬の防犯効果は他のペットと比較して高めです。
ただし、防犯効果はペットの種類や性格によって異なります。ペットの防犯効果について詳しくご説明します。
空き巣が下見でペットの有無を確認する理由
空き巣が下見の際にペットの有無を確認する理由は、ペットを飼っている住まいでは犯行をスムーズに行えない可能性があるからです。
特に、犬は知らない人に対し吠えたり、噛みついたりする印象が強く、空き巣を警戒させる効果があります。鳴き声が近隣住民の注意を引くため、目立つことを恐れる空き巣が犯行を諦める可能性を高められるのです。
警察庁の「住まいる防犯110番」では、空き巣が家の下見でチェックする項目として、「犬がいる」ことが挙げられています。また、侵入を諦めた理由にも、「犬を飼っていた」が挙げられているため、犬に防犯効果があることがわかるでしょう。
出典:住まいる防犯110番「侵入者プロファイリング<心理と行動-1>」
住まいる防犯110番「侵入者プロファイリング<心理と行動-3>」
ペットの種類によっては防犯効果がない
吠えたり、噛みついたりできる犬の防犯効果は高めですが、他のペットはどうなのでしょうか。実は、ペットの種類によっては、空き巣にとってまったく脅威になりません。
例えば、警戒心が強く環境の変化に敏感な猫は、空き巣が家の中に入り込んだ際に、身を隠してしまいます。ほかにも、鳥類や爬虫類、うさぎやハムスターなどの小動物も、空き巣に反応しづらいため、残念ながら防犯効果はありません。
ペットの性格によっては防犯効果を期待できない
ペットの性格も、防犯効果に大きく影響します。防犯効果が高いとされている犬でも、性格によっては防犯効果が期待できません。
例えば、人懐っこい犬や怖がりの犬、吠えない犬や温厚でおっとりした犬は、空き巣に対して吠えたり警戒したりすることが少ないため、防犯効果を期待しない方がよいでしょう。
ペットがいてもホームセキュリティは設置できる!
ペットを飼っているご家庭には、ホームセキュリティを設置しにくい傾向がありますが、工夫すれば導入も可能です。また、「ペットを飼っているから安全」との考えは非常に危険で、ペットを飼っているからこそ生じる隙や油断につけ込んで、あえてペットを飼っているご家庭を狙う空き巣もいます。
家族とペットが安心して暮らすためにも、ホームセキュリティの導入を検討してみませんか?
ホームセキュリティを導入するなら、CSPのホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ+」をおすすめします。
「ファミリーガードアイ+」は、24時間365日、生活を見守ります。異常が発生した際には即座にCSP指令センターに通知されるため、ペットを飼っているご家庭でも安心して外出できるでしょう。
また、ペットを飼っているご家庭では、火災・ガス漏れなどの緊急事態が発生した際に、ペットの安全を確保するための迅速な対応が求められます。「ファミリーガードアイ+」では、緊急時にパトロール員が駆けつけるサービスを提供しているので安心です。
「ファミリーガードアイ+」は、スマートフォンアプリを使って簡単に操作・管理ができます。アプリを通じてセンサーの設定を変更したり、警備をオン・オフしたりすることも可能ですので、ペットの状況に合わせて柔軟に対応できます。
ペットと一緒に安心して暮らせるセキュリティ環境を整えるために、「ファミリーガードアイ+」は非常に役立つのでおすすめです。
まとめ
CSPのホームセキュリティなら、ペットと共存できます。ワイヤレス空間センサーのペット用レンズを使用し、警戒する範囲や高さを調整するなど、ペットに配慮した柔軟な対応が可能ですので、ぜひ「ファミリーガードアイ+」の導入をご検討ください。
CSPはペットを飼っているご家庭へのホームセキュリティの設置の実績も豊富で、ペットによって生じる誤作動を減らす工夫も熟知しています。住まいに合わせた最適なプランをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ+」の詳細ページはこちら↓
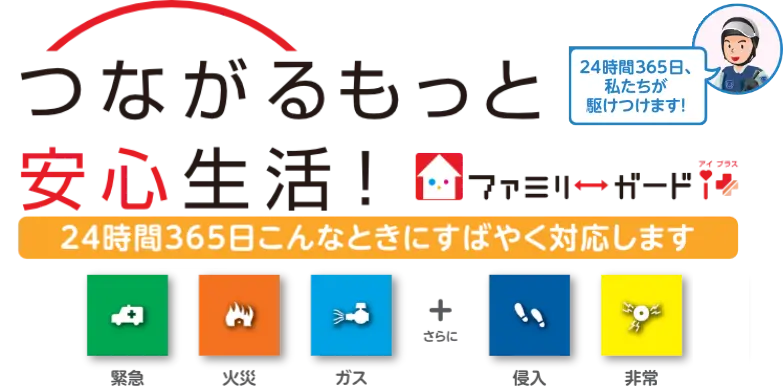
ホームセキュリティサービス「ファミリーガードアイ+」
シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」の資料請求やお見積り依頼はこちら↓
おすすめ記事